── 不登校小学生のオンライン家庭教師 つむぎさんインタビュー
子どもが学校に行けない日が続くとき、「学習の遅れが心配…」「どこから手をつけたらいいのだろう」と胸がざわついた経験はありませんか。
つい“学校のペース”を基準に考えてしまい、親子ともに苦しくなってしまうこともあるかもしれません。
でも、「学校に行かない=学びが止まる」ではありません。むしろ家にいるからこそ育つ学びがあります。
今回お話を伺ったのは、12年の教員経験を経て、不登校のお子さんの在宅学習をオンラインで支えるつむぎさん。
不登校のお子さんを支える親御さんへ——安心して一歩を踏み出すヒントになるはずです。ぜひご覧ください。
■教室の外でも、学びは育つ——つむぎさんが“オンライン家庭教師”を選んだ理由
つむぎさんは約12年間、小中学校で教員を務め、特別支援学級や別室登校(自立登校)の子どもたちの支援に携わってきました。
特別支援や別室登校のお子さんとは相性が良いと感じていましたが、学校では異動で毎年関わりが変わります。もっと継続的にサポートしたいという思いが強くなったと語ってくれました。
また長く学校に関わる中で、「子どもと学びを支えるのは好きだけれど、学校という組織で続けることには迷いがある」と気づいたことも、転機となりました。
「子どもが好きで学習をサポートする仕事も続けたい――
そう考えたとき、教員を続けるよりも自分に合った形を模索し、オンラインでの学習サポートに行き着きました」
こうして、子どもたちの“その子らしさ”に寄り添う現在のスタイルへと歩み出しました。

■“学校の進度”はあくまで目安——「今できるところ」から始める
不登校期に多くの親御さんが心配するのが「学習の遅れ」です。つむぎさんはその気持ちに共感しつつも、こう話します。
「学校の進度はあくまで目安。そこにこだわり過ぎると親子ともに苦しくなります。
まずは“今できていること”から始めましょう」
また、復学を望むかどうかによってもサポートの仕方は変わります。
「もし“戻りたい”という気持ちがあるなら、復学した時に授業とのギャップでまたつまずかないよう、無理のない範囲で早めに追いつける道筋を一緒に考えます」
ただ、進度にこだわり過ぎて親子が苦しくなるのは本末転倒。あくまで“今のその子”に合ったペースを一緒に探していきます。
■親の焦りと、子どもの気持ち——方向をそろえるところから
「学年が変わったら戻れるかな」「いつになったら通えるだろう」——親がそう考えるのは自然なこと。
「早く戻ってほしいと思うのは親の気持ち。
でもお子さんも同じ気持ちとは限りません」
その焦りがそのまま子どもに向かうと、「戻れない自分はダメだ」と追い詰めてしまう恐れがあります。
大切なのは親自身が不安を認めつつ、それを子にぶつけないこと。
「自分は不安なんだ」と受け止め、子どもの歩幅に合わせる姿勢が、学びを再開する土台になるとつむぎさんは話します。
■在宅学習の最初の一歩——ハードルを“限りなく低く”
家で学びを始めるとき、最初の壁は「とりかかり」。いきなり宿題の束をドン、と渡しても続きません。まずは“やれた感覚”を増やしましょう。
「いかにハードルを下げるかが大切。
ゲームが好きなら学習アプリから“ちょっと一緒に”でもOK」
親が同じ時間に自分の学び(読書や資格の勉強など)を始めるのも効果的。「あなたも、わたしも少しがんばる」。この並走感が子どもの「やってみよう」を後押しします。
また「机に座って30分」という形にこだわる必要もありません。料理をしながら数を数える、ペットの散歩中に季節の変化を話題にする——生活そのものが学びの材料になります。

■“何分やれば安心?”より、“続けられる時間”を一緒に決める
「勉強は何分やれば安心か」という基準は、実は親の安心のためになりがちだとつむぎさんは言います。
「学校では長時間学びますが、家で同じようにするのは現実的ではありません。
大切なのは親が時間を決めるのではなく、子どもと一緒に“続けられる時間”を話し合うことです」
最初は5分からで十分。1週間続けられる時間を一緒に決め、できたら少しずつ延ばしていく。週1回長時間より短時間を毎日積み重ねる方が力になるのです。
■「最低これだけ」で学びを切らさない——やる気が出ない日の小さな約束
家庭では学校と違って誘惑が多く、「今日はやりたくない」と感じる日が必ずあります。そんな時こそ学びを完全に切らさない仕掛けを作っておくことがおすすめです。
「“最低これだけ”という小さな約束をあらかじめ決めておくんです。
たとえば漢字1文字、計算1問など。ほんの少しでも続けておくことで、次に取りかかるハードルが下がります」
ただし、体調や気持ちがどうしても整わない日もあります。
「無理にやらせる必要はありません。
『今日は休むけど、明日はこれをやろう』と次につながる言葉を添えて、一度受け止めてあげてください」
こうした小さな約束と次への一言が、積み重ねてきた学びの流れを途切れさせない鍵になるんです。
■続けやすくする小さなコツ——“量を見せない・できたを見える化”
子どもは“山のような問題集”を見ると、それだけで気持ちがしぼんでしまいます。
「1枚だけコピーして渡す、タイマーより“量”で区切るなど、見える量を小さくする工夫が効きます」
できた日はカレンダーにシール。回数が増えるほど自信が育ちます。「できた」が見えると、次に進む力が自然と湧いてくるんです。
シールが増えるたびに「今日もやれた」という達成感が目に見える形で積み重なり、子ども自身が学びを前向きに捉えるきっかけになります。
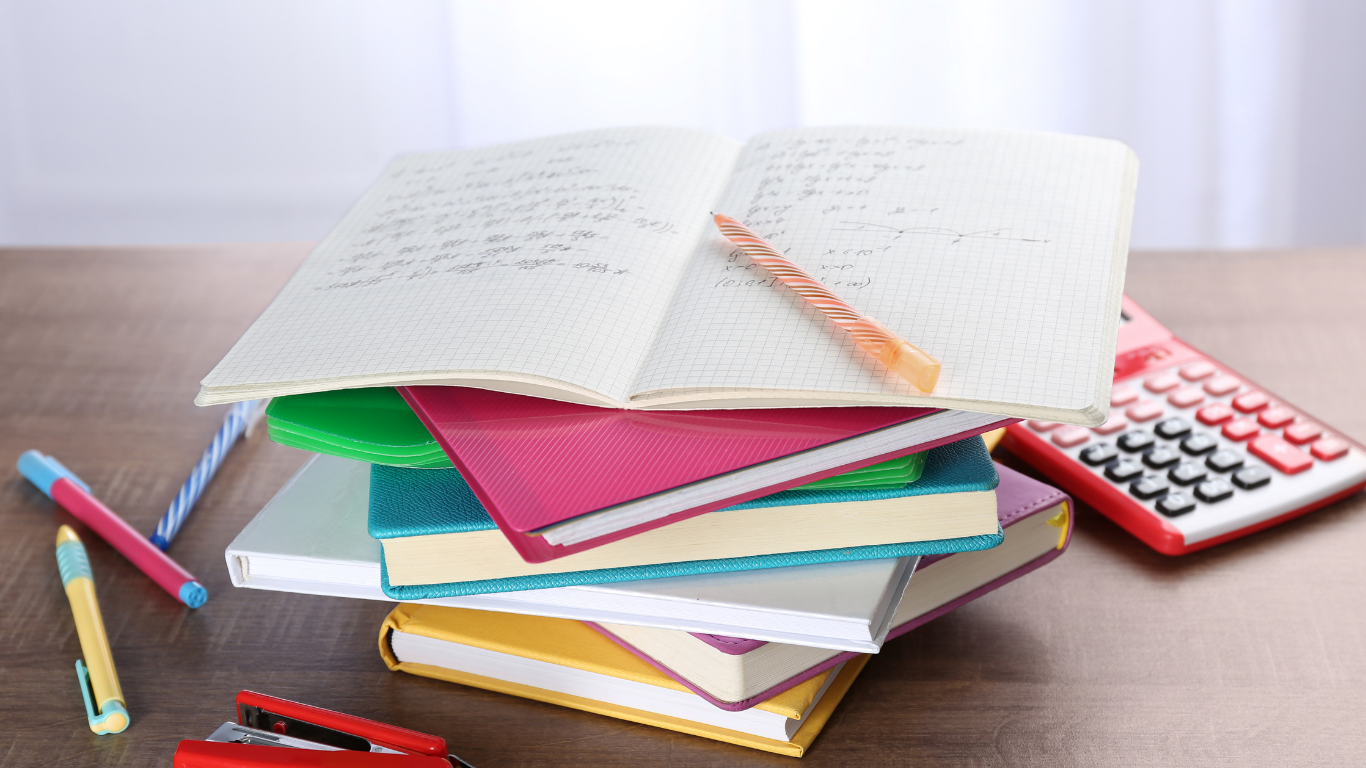
■“どうせできない”をほどく——自己肯定感を育て、学びへの意欲へつなげる
「不登校の子どもたちは、学校での比較や経験の少なさから自信を失い、自己肯定感が低くなっていることが多いんです」
つむぎさんは、現場で何度もその姿に出会ってきました。
「周りはできるのに自分はできない」「しばらく勉強していないから、どうせ無理」——こうした自己評価が根っこにあると、いくらタスクを提示しても手は動きません。
だからこそ最初にやるべきことは、勉強そのものを押し込むことではなく、“自分はやればできる”という感覚を取り戻すことなのかもしれません。
■“得意”から学びはひらく——教室で起きた変化
印象的だったのは、かつて担当した“工作が得意”な子の話。2年近く勉強ゼロだったその子は、工作に没頭していました。
「得意をひたすら認め続けたら、家で宿題を少しやるようになって、やがて自分から九九や漢字に取り組むようになったんです」
自信の起点がひとつあると、学びは動き出す。勉強の入り口は、教科書の外にもたくさんあります。
■さいごに
学校に行かない日があっても、学びは止まりません。基準を学校だけに置かないこと。そして、子どもの「得意」をしっかり認めて褒めることで自信を育て、それがやがて学びへの意欲につなげることが大切です。
必ずしもプリントや問題集からでなくて大丈夫。料理や動画の感想だって“学びの種”です。親御さんも楽しみながら一緒に始めてみてください。
親子の歩幅に合ったやり方で、今日の小さな一歩を踏み出しましょう。
― つむぎさんのオンライン家庭教師サービスについて ―
基本プランは 週1回・60分。集中がまだ難しい場合は 30分×2回 や 30分週1回 など、状況に合わせて柔軟に調整。レッスンでは、お子さん一人ひとりのペースを尊重しながら学習をサポートします。
また、保護者の方からの要望を受け、お母さん・お父さん自身のサポートにも力を入れています。
在宅学習の始め方を具体的なステップでまとめたテキストの提供や、保護者のメンタル面を支える伴走など、親子を両輪で支える体制を整え、まもなくスタート予定です。
お子さんの学びを止めず、自信を育てる第一歩として、ぜひつむぎさんの不登校小学生オンライン家庭教師を活用してみてください。
.png)
つむぎ|不登校小学生のオンライン家庭教師
小・中学校での教員経験12年。特別支援/別室登校の子どもたちの伴走を長く担い、現在はオンラインで不登校期の学びをサポート。お子さんのペースに合わせた柔軟なレッスン設計と、保護者へのやさしい伴走が特徴。
Instagram: @tsumugi_.teacher
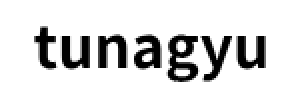
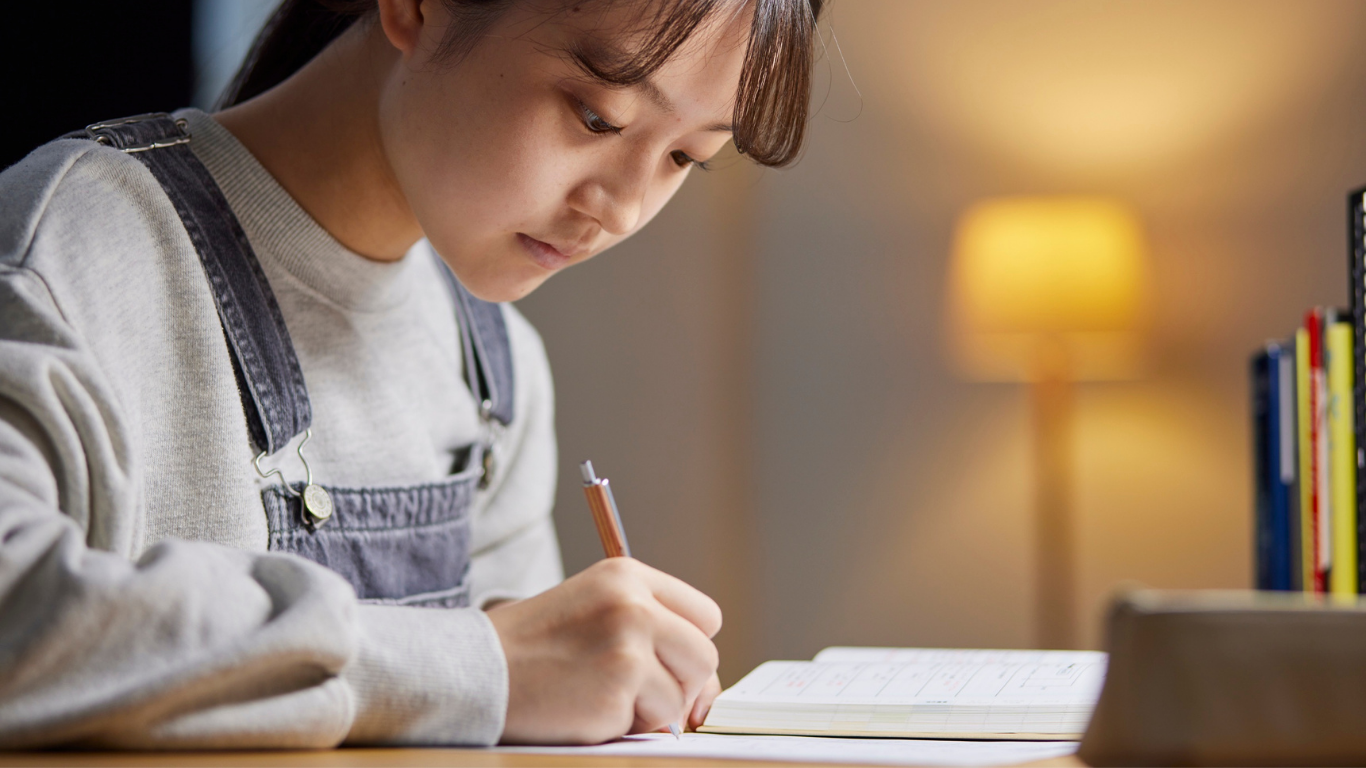
 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 258
閲覧数: 258
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 244
閲覧数: 244
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 203
閲覧数: 203