── 高橋南海さんインタビュー
あなたは、ついつい「子どもが良い結果を出したときだけ褒めてしまう」こと、ありませんか?
確かに、褒められると子どもは嬉しそうに笑い、モチベーションも上がるように見えますよね。実際、全国の保護者の約7割が「褒めて育てたい」と考えているというデータもあります(ベネッセ教育総合研究所調べ)。
でもその一方で、「褒めたあとの子どもがプレッシャーを感じている」「思ったほど自己肯定感が育っていない」と感じることも少なくないのではないでしょうか。
実は、子どもの自己肯定感を育てるには、「褒める」よりも“勇気づけ”の声がけが大切になるんです。
そこで今回は、日常でのアドラー心理学の使い方を伝えている高橋さんに、「勇気づけ」を取り入れるための具体的な考え方や日常での実践法を伺いました。子どもの自信や心の強さを育みたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
■「褒める」と「勇気づけ」は、異なる行為
「子育てでは“褒めて育てる”ってよく聞きますよね。
でも実は、そこに気をつけるポイントがあるんです」
高橋さんが強調するのは、「褒める」と「勇気づける」の本質的な違い。
たとえば、テストで100点を取った子に「すごいね!」と声をかける。この“褒め”が良くないわけではない。ただし、それが「100点だからすごい、50点だからダメ」と“評価”が基準になってしまうと、子どもは“結果”にばかり価値を見出してしまう。
「“勇気づけ”は、100点でも50点でも、どんな結果でも『あなたは素晴らしい』と伝える声かけなんです」
つまり、「結果」ではなく「存在そのもの」に目を向ける。それが、勇気づけの本質だという。

■親子の関係を変えてしまう「褒める」の2つのポイント
高橋さんは「褒めることには、実は2つのポイントがある」と語ります。
1つ目は、親が子どもを“評価する立場”に立ってしまうこと。親子が上下関係になり、対等な信頼関係が崩れてしまいます。
2つ目は、結果への依存です。「100点を取ったから褒められる」「結果が悪いと褒められない」という経験が続くと、子どもは「良い結果を出さないと価値がない」と思い込み、挑戦する気持ちを失いやすくなります。
「結果って、どれだけ頑張ってもコントロールできないことがあるんです。
だからこそ、その子自身の存在や努力のプロセスを認めてほしいですね」
■自己肯定感を育てる、日常の“ひとこと”
高橋さんが日々実践しているのは、とてもシンプルなこと。
「“生まれてきてくれてありがとう”とか、“そこにいてくれるだけで嬉しい”とか。
特別な日じゃなくて、何でもない日にこそ、そう伝えるようにしています」
また、努力や過程を認めることも大切。
「50点だったとしても、結果の前の過程でしっかり勉強していたのであれば“よく頑張ったね”と伝える。
そうすれば結果に関係なく、“自分には価値がある”と実感できるようになります」

■「勇気づけ」が子どもを強くする
では、実際に“勇気づけ”を意識すると子どもにはどんな変化が起きるのでしょうか?
「結果に縛られず、『ここにいるだけで価値がある』と思えるようになると、子どもは自分を信じられるようになります。
他人の評価に振り回されなくなるので、学校で友達と気持ちのすれ違いがあっても『私はここにいるだけで価値がある』と思うことができたら乗り越えられるんです」
高橋さんは、「勇気づけは、子どもが困難、課題に立ち向かう勇気になる」と話してくれました。
■見守ること=信じること
とはいえ、子育て中には「手を出したくなる瞬間」がたくさんある。失敗させたくなくて、つい先回りしてしまう。
「先回りするということは、“この子にはできない”事を前提にしているということ。
見守るというのは、“できると信じる”ことなんです」
失敗しても「次はできるよ」と声をかけ、成功すれば「できたね」と認める。
その繰り返しが、子どもの自己肯定感を静かに支えていく。

■親がイライラしてしまったとき、どうすればいい?
「イライラしない親なんて、いないですよ」と笑う高橋さん。
「大事なのは、“イライラしてしまう自分”を責めないこと。
そして、“イライラの正体”をちゃんと見てあげることです」
たとえば、時間通りに出かけたいのに子どもが牛乳をこぼした。怒りの本質は、「子どもがこぼしたこと」ではなく、「自分の予定が狂ったこと」。
「イライラって、実は“自分の目的が達成できないこと”への反応なんです。
だから、『これは私のイライラだ』と客観視できると、感情に飲み込まれなくなります」
■まずは、“親自身”を勇気づけることから
最後に、高橋さんが最も伝えたいこと。それは、「まずは自分自身を勇気づけること」。
「“何もしなくても自分には価値がある”って、毎日自分に言ってあげてください。
アファメーションという有名な手法です。繰り返す事で脳に定着し本当だと思えるようになっていきます。」
「親が自分を認められるようになると、子どもへの接し方も変わります」
■さいごに
子どもの自己肯定感を育てたい。そう願う一方で、結果ばかりに目を向けてしまったり、思うように関われなかったり……。そんなもどかしさは、どの親にもあるものです。
でも、「ただそこにいてくれるだけでうれしいよ」と伝えることから、すべては始められます。
難しい理論より、日々の“ちょっとした声かけ”が、子どもの未来を変えていきます。
今日の記事の中で心に残った言葉があれば、ぜひ明日からひとつだけ、試してみてください。
それが、親子の間にあたたかな変化を生み出す一歩になります。

高橋南海さん
アドラー心理学をベースに、子育てママ向けにアドラー心理学の使い方をInstagramや講座で発信中。
自分で「選べる人生」を手に入れるをテーマに、心の整え方や関わり方を日常に落とし込んだ実践的なサポートを行っている。
2人目の出産後にパニック障害を経験。薬に頼らず、アドラー心理学やコーチング等を実生活に取り入れる事でパニック障害を克服。その経験を同じように悩む人に伝えたいという気持ちから、学びと実践を重ねてきた。
今では全国のママたちに向けて「心の捉え方」を伝える活動を行っている。
高橋南海さんの詳しい情報はこちらから
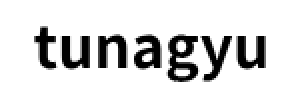

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 247
閲覧数: 247
 閲覧数: 230
閲覧数: 230
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204