── まみさん インタビュー
あなたは、ついつい「そのうち話すよね」と思いながら、毎日の声かけがだんだん不安混じりになっていませんか?
確かに“発語”はわかりやすい成長のサイン。ついそこに目が向きますよね。
結果として「まだ話さない…」「どう関わればいいの?」と悩みが深くなることも多いと思います。
でも実は、子どもの“いま”に合わせ、コミュニケーションの土台を丁寧に育てると、発語に必要な力が揃っていくんです。
そこで今回は、小児専門の言語聴覚士まみさんに、自閉っ子のことばの発達を支える関わり方をうかがいました。
発語に焦りやすいママこそ、最後まで読んでみてくださいね。
■ 医療・教育・福祉を渡り歩いて見つけた答え——「家族に寄りそう支援」
言語聴覚士(ST)として12年目。昨年春、訪問支援とオンラインでことば・コミュニケーションのサポートを行う「ことばと発達の相談室ことはぐ」として独立。名前には、「子どもとハグする」と「言葉を育む」を重ねた想いが込められています。
同時期にInstagramで自閉スペクトラム症のお子さんのことばやコミュニケーションに関する情報の発信を開始。現在はマンツーマンで自閉っ子ママをサポートするオンライン講座を主宰して2年目になります。
「言語聴覚士になって12年目。最初から小児しか考えていませんでした。医療・教育・福祉を渡り歩いて、訪問とオンラインで親子に伴走しています」

■ 気づきは“発語”ではなく“通じ合う”から
印象的だったと語ってくれたのは、診断を受けたばかりの親子のお話。ママは「この先どうしたら…」と不安でいっぱい。お子さんは、「り(りんご)」や「う(ぶどう)」のような単音が少しだけ出ている状態。
はじめての変化は、ことばより先にやってきました。テレビを見ながら、お子さんが「ママ、見て!」と指差し。それまで見られなかった“共有の指差し”が生まれ、ママの方へ振り向いて「これ、見て」をと伝えられたのです。
その日を境に、「ほんとうだね」と同じものに一緒に笑い合える時間が増えていったそう。。通じ合う経験が積み重なるにつれ、ママの不安も少しずつほぐれ、2語文、3語文へと発語も自然に広がっていきました。
約1年後、うれしい知らせが届きました。家族ぐるみのお出かけで、いつもは輪から離れてしまっていたお子さんが、集合写真のまんなかでポーズ。移動の車内でも、ほかの子に「それ見せてよ」と自分から声をかけられるようになっていました。
このエピソードが教えてくれるのは、最初の一歩は“発語”ではなく“伝えたい気持ち”だということ。ここがつながると、ことばはあとから追いかけてきます。
「ことばの発達は理解 → 発語 → 会話の順で積み上がります。
発語だけを目標にせず、“コミュニケーション”という土台を先に育てることが近道です」
■ 子どもの視線に降りる——“教えたい”より“いま見てるもの”
まみさんが大切にしているのは、大人が教えたいものではなく、子どもがいま見ているもの・興味があるものに言葉を添えること。
大人はつい「これはチューリップだよ」「あれはね…」と伝えたくなりますが、子どもが注目していないと、言葉と物が結びつきにくいんです。
「自閉っ子は“自分の気になる”が強い子が多い。
だからこそ、興味を持って見ているものに『つるつるだね』『冷たいね』『石だよ』と、感じたこと+言葉を重ねると、五感とことばが結びつきます」
■“実況”と“まねっこ”で、コミュニケーションのスイッチを入れる
コミュニケーションに、特別な教材は不要です。動作の実況や大人のまねっこから始めてみましょう。
「車でブーンと走らせていたら『ブーンだね』『赤い車だね』と簡単でOK。
また、お子さんの真似を大人がする——『あー』って言ったら一緒に『あー』。
それだけで“同じことしてる人がいる”と気づきが生まれて、コミュニケーションにつながります」

■ 控えておきたい関わり——“ことばのシャワー”と“一音トレーニング”
『もっと話しかけて』と言われることもありますが、量を増やせばいいわけではありません。
「理解が育っていない段階で矢継ぎ早に声をかけても処理できません。量よりタイミングです」
また、「あ・い・う・え・お」など単音だけを練習させる方法は、音を出す練習としては意味がありますが、言葉の意味の理解や発語にはつながりにくいです。
言葉の発達が未熟なお子さんは「リ・ン・ゴ」と一音ずつではなく、「リンゴ」とまとまりで聞き取ります。ゆっくり区切るより、自然な速さで、意味と結びついた言葉を聞かせるほうが効果的です。
■ きょうだいは“関わりの見本”——家族で対応をそろえる
きょうだいを“お世話係”にしなくて大丈夫。自閉っ子への対応を、無理にきょうだいに頼む必要はありません。自然な関わりのままでOKです。
「きょうだいの自然なまねっこはとても関わりの参考になりますよ。
お兄ちゃんが何気なく自閉っ子である弟の仕草を真似すると、ふっと弟が気づいて笑い合い、やりとりが生まれるということもありました」
ぜひ自然な関わりを大人がヒントにしてみてください。
■ 見えにくい土台を育てよう
話し言葉は目に見えて分かりやすい反面、出てこないと不安になりますよね。
けれど、ことばが育つまでには“見えにくい土台”の積み重ねがあります。この土台が育っていないと、発語につながりにくいんです。
「いちばん下には安定した生活リズム。
その上に、安心・安全な親子関係、からだや感覚の発達、そして物への興味や理解が重なって、最後に“発語”という分かりやすい芽が出てきます」
発語だけが気になってしまうのは自然なこと。無理に「大丈夫」と自分の気持ちに蓋はしないでほしいと思います。ママ自身の素直な気持ちも大切にしながら、言語聴覚士(ST)や療育のスタッフなどの専門家に相談し、いまの段階でできる“土台づくり”に目を向けてみてください。
ひとりで抱え込まず、誰かに頼りながら進めていきましょう。そのほうがママの安心にもつながり、結果としてお子さんのことばの育ちをやさしく後押ししてくれます。
■ 興味の“幅”をやさしく広げる
発語は、言葉と“物・体験”が結びつくことで育ちます。だから遊びの中で、「教える言葉を増やす」よりも、子どもの興味を広げる関わりが効果的です。
「自閉っ子は関心がグッと一点に集まりがち。
虫が好きなら『アリさんはりんご食べるよ』『ちょうちょはバナナ好きだね』と“食べ物”へ広げるなど、好きから世界を広げていきます」
放っておくと、虫の難しい名前は言えるのに「りんご」が分からない、のように語彙が偏りがちに。大人が意識して”興味の幅”を広げることが大切です。
また、知的発達がゆっくりなお子さんは、できるだけ早い時期から「相手への意識」と「言葉の理解」を促す関わり(指さし・身振り・実物体験に短い言葉を添える)を重ねると、育ちがスムーズになります。

■“未熟=伸びしろ”で見る発達
「脳の発達が”悪い”ではなく、”育ちの道筋が違う——“未熟”というイメージの方が近いです。悪いではなく“育ちの道筋が違う”。意識して関われば、伸びる領域がたくさんあります」
大切なのは「劣っている」ではなく「まだ育ち途中」と捉えること。
たとえば、前頭前野の発達がゆっくりだと切り替えやブレーキが難しく、かんしゃくや強い不安は脳レベルでの防衛反応が出やすいことが関係します。
ことばの発達は大脳皮質という脳の一番外側の部分の成長に左右され、追いつかないと本能的な反応が先に出やすくなります。つまり問題ではなく“ペースの違い”。
周囲が理解し、環境や関わり方を整えれば、その子の力は発揮されやすくなります。
■さいごに
「話てほしい」——そう願う気持ちは、もちろんどのママにもあります。焦ってしまう日があっても、それは自然なこと。無理に打ち消さなくて大丈夫です。
ただ、発語だけをゴールにしていると土台の成長が見えにくくなってしまいます。
ことばは、伝えた い気持ちを土台にゆっくり育っていきます。今日からできる一歩は、とても小さくてOK。たとえば、 お子さんが見ているものにそっと言葉を添える、今の動きをやさしく言葉にする、となりでママが まねっこしてみる——そして、生活リズムと“安心”を整える。
そんなやわらかな積み重ねが、こと ばの土台になっていきます。
そして何より一番大事な土台は、ママが「安心」してお子さんと関われること。 不安でモヤモヤした気持ちのままでは発達の土台も揺らぎがちです。
発達の遅れは育て方のせいではありません。そして、お子さんの悩みを一人で抱える必要もありません。
お子さんのことを一緒に考えてくれる専門家とチームになって、ママも「安心」の土台を作ってくださいね。
.png)
まみ|言語聴覚士(小児専門)
医療・教育・福祉の三分野で小児のことば支援に従事。現在は「ことばと発達の相談室ことはぐ」として訪問・オンラインで親子に伴走。Instagramでは自閉っ子のことばの発達に特化した情報を発信しながら、自閉っ子ママのためのマンツーマン講座を主宰している。
まみさんの詳しい情報はこちらから
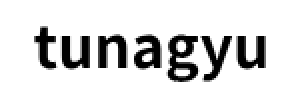

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 258
閲覧数: 258
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 244
閲覧数: 244
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 203
閲覧数: 203