── 岡田陽子さんインタビュー
キッチンデビューさせたいけれど、忙しさや散らかり、安全が心配で…」と足踏みしていませんか。子どもの「やってみたい」に胸が動きつつ、始め方に迷うこと、ありますよね。
いきなり一緒に“作ろう”と力が入るほど、焦りや叱りが増えてしまうことも。
でも、キッチンデビューは思っているよりとてもやさしい始め方で大丈夫なんです。無理をせず「いっしょにいる」「触れてみる」から。タイマーを押す、冷蔵庫をのぞく——それだけでも、ゆっくり学びは育っていきます。
こうした“台所時間の魔法”は、子どもの食への興味や心をあたため、考える力と親子の対話を豊かにしてくれます。
今回は、肩の力をふっと抜いて始められるキッチンデビューのヒントと魅力を、台所育児を発信してきた元幼稚園教諭の岡田陽子さんにうかがいました。
■「台所育児」との出会い:生きる力に直結する学び
岡田さんの原点は、幼稚園教諭として子どもに寄り添ってきた経験と、母から学んだ“食の力”にあります。高校時代、外食中心の生活でアトピーに悩んだことをきっかけに、「食べたもので体はつくられる」と実感。
やがて出会ったのが、台所育児の先駆け・坂本廣子先生の講演でした。
「台所は学びの宝庫。生きるために必要なことがぎゅっと詰まっている——その言葉に衝撃を受け、独身のときに子ども用“本物”キッチンセットをその場で購入したほどでした」
現在は食育関連企業で、大人の食育を広げる仕事に携わりつつ、個別の依頼に可能な範囲で対応されています。

■台所は五感とことばをひらく場所
「料理は五感全てを使うことができるとても贅沢な時間です。」と岡田さん。
切る音、揚げる音、ゆらめく香り、色の変化、野菜の断面の“発見”。子どもは目を輝かせ、ことばが自然と引き出されます。
「娘が、揚げ焼きの音を“雨の音みたい”と言ったのが印象的でした。大人には“ジュージュー”でも、子どもの耳には違って聞こえる。冷蔵庫の中を初めて見せたとき、“キラキラしてきれい”とも。
台所は、忘れていた感性を親にも思い出させてくれます」
“おいしい”は、味だけの体験ではありません。見る・嗅ぐ・触る・聞くがそろって、初めて「食べてみたい」に結びつく。
たとえばピーマン——断面のかたちの面白さや、加熱で香りが変化する体験が、苦手の入り口をやわらげてくれます。
■最初の一歩は「作らない」からでもいい
「台所に立つ=一緒に料理を完成させる」必要はありません。ハードルを下げるのが継続のコツ。
形から入る:エプロン、帽子、子どもサイズの“本物”の道具でやる気スイッチを。
“いる”から始める:キッチンタイマーを押す、音を聞く、冷蔵庫や引き出しを探検する。
“見る・聞く・触る”の担当:食器を選ぶ、卵を数える、皿拭き、じゃがいもを洗う——作ることに繋がるとても大切な時間です。
“一緒に作らなきゃ”ではなく、“一緒に台所にいる”で十分。そこで小さな役割を渡していければ、それで大成功です。
■年齢より“やりたい気持ち”を尊重する
包丁や火は怖い——そんな不安は当然です。ただし判断基準は「年齢」だけではありません。
「例えば、踏み台にしっかり立てるようになったら、包丁や火を使わせてもいいかもしれません。
怖いと感じるなら、バターナイフでバナナを切るなど“本物感を残した代替”から。
親がハラハラするなら無理はしないことも大切です」
“ダメ”で終わらせない。危ない工程は避けつつ、できる形に設計して“やりたい”を守る。これが、自己効力感(できた!)の芽をつぶさない関わり方です。

■親の心の準備と道具選びが、安心をつくる
包丁は「危ないもの」ではなく、“切るための便利な道具”。
用途・持ち方・置き方を先に伝えれば、怖さはぐっと減ります。岡田さんの推しは、子どもサイズだけど本物。
「サンクラフトの子ども包丁は持ち手・刃のサイズがフィットしやすく、7点セットなどトング・ピーラー・フライ返しも子どもが扱いやすい形。
ステンレスの質感や重みが“特別な自分の道具”という特別感がでます」
親の覚悟 × 安全な環境 × 扱いやすい本物。この三点がそろえば、体験はより豊かに、安心して進みます。
■忙しい日でもできる“ロスタイム回避”の工夫
夕方の台所は、とにかくタイト。だからこそ、時間帯をずらす・役割を絞るの発想を。
明日の朝ごはん係:夜は親が作り、翌朝の下ごしらえ(ぶどうを房から外して洗う・器を並べる)を子どもが担当。
最後の仕上げ係:しょうゆを回しかける・盛りつけるなど大事な一手をまかせて達成感を。
「コックさん/お母さんやお父さんみたい」の言葉かけ:役割名で自己像を上げる。
また、横並びで立つと、面と向かうより感情がぶつかりにくく、穏やかなコミュニケーションが生まれます。
“最初から最後まで”を理想にしない。“ここまでできた、すごい”を積み上げるのが続く秘訣なのです。
■台所が変える、親子のコミュニケーション
台所では、子どもの言葉と表情が豊かにこぼれます。
岡田さん自身、娘さんの感性に触れて「もっとこの子の声を聴きたい、娘の考えや表現に触れたい」と思い、口出しを減らして見守ることが増えたと言います。
「“子どもの困ったところ”より、“好きなところを10個”挙げてみる。好きなところとなると意外と5個くらいで詰まってしまう方って多いと思います。
台所育児を続けると良いところがたくさん見えてくる」
親の見方が変わると、子どもも違う表情を見せてくれます。また問いかけの質も変わります。
「卵を2個持ってきてくれる?」「5人分の目玉焼きには卵が何個必要かな?」——算数・国語・生活科が、自然に台所でつながっていきます。

■“食べたい・やってみたい”は、知ることから芽生える
断面の不思議、色の変化、火の音、香りの移ろい。変化をいっしょに観察することが、苦手食材の突破口になります。
「この匂い、火を通すと変わるかな?”“切ってみたらどんな形?」
知る→興味→ひと口の流れが起きます。全部がうまくいかなくてOK。“今日はここまで”で十分なんです。
■さいごに
教えなきゃ・全部やらせなきゃは手放して、発見をいっしょに喜ぶことから。作らなくても、冷蔵庫を見る・食器を選ぶ——できることはたくさんあります。小さく始めて、続ける。
そうして生まれるのが、親子で向き合う時間と、五感でひろがる学び——それが“台所時間”の魔法なんです。
では、今日あなたとお子さんはどんな「小さな一歩」から始めてみますか?
まずはお子さんと、一緒に台所に“いる”時間を楽しみましょう。
.png)
岡田 陽子
元幼稚園教諭。上級食育指導士/おうち食育協会認定講師。キッザニア東京 立ち上げメンバー。台所育児を中心に、キッチン&食卓で食を楽しむ関わりを提案。現在は食育関連企業で大人の食育に携わりつつ、個別の依頼に可能な範囲で対応。
Instagram:@yoko_okada269
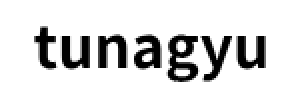

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 255
閲覧数: 255
 閲覧数: 230
閲覧数: 230
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204