──あおいさんインタビュー
「うちの子、どうしてやる気が出ないんだろう?」「言っても聞かないし、自分から行動してくれない…」
そんな風に悩むママやパパも多いのではないでしょうか。
実は、子どもの“やる気”には、声かけ以前にやる気を引き出す本質があったんです。
それは「言い方」でも「叱り方」でもなく、“信頼”という土台から始まるもの。
今回は、チャイルドコーチングの手法を取り入れて子どもとの関係性を大きく変えてきた、あおいさんにインタビュー。
「やりなさい」と言わなくても、自分から「やりたい!」があふれる子どもになるためのヒントを伺いました。
■やらせる子育てに疑問を感じていた
「子どもには、自立した人になってほしい」
そんな思いを抱いていたあおいさんは、長男の幼少期から知育教室や習い事に積極的に取り組んできました。
けれども、あるとき教室で前向きに取り組んでいない長男の姿に気づいたといいます。
やる気が見えない様子に戸惑いながらも、「子ども自身が“やってみたい”と思わないと、どんなに環境を整えても効果は出ない」と痛感したといいます。
そして辿り着いたのが、チャイルドコーチングでした。

■チャイルドコーチングで変わった、子どもの姿勢
コーチングを学び始めたのは、長男が4〜5歳の頃。
学んで実践を通じて、お子さんが変化していきました。
「将来の夢や、やりたいこと(お菓子作りやピアノなど)も見つかり、努力する姿が見られるようになったので、コーチングに出会えて本当によかったと感じています」
長男は今、小学4年生。
「ここまで頑張ってみる」「目標を決めて努力してみる」など、納得したうえで行動する力が育ってきたといいます。
うまくいかない時も、「人のせいにせず、自分の責任として受け止める姿勢」まで見られるようになったそうです。
■“やりたい”は、土台があってこそ育つ
コーチングを子育てに取り入れるうえで、まず重要なのは“親の心構え”だとあおいさんは語ります。
「いくら声かけを工夫しても、子どもが“信頼できる人からの言葉”として受け取っていなければ、響かないんですよね」
つまり、「何を言うか」よりも「誰が言うか」。 信頼されている大人からの言葉は、スッと心に届く。 子どものやる気を育てるには、「信頼関係」という土台が不可欠です。
■“信頼”の積み重ねは、聴くことから始まる
では、その信頼関係はどうやって育てていくのでしょうか?
「まずは“聴くこと”だと思います。興味を持って話を聴いてあげるだけで、子どもは『自分の話を聞いてくれる人なんだ』って思えるんです」
たとえば、子どもが好きなゲームについて「どうやったら勝てるの?」「今どんなことしてるの?」と具体的に聞いてみる。
たった1日10分でもいい。
“ながら”ではなく、“ちゃんと向き合って聴く”時間が、信頼を育てていく鍵になります。

■親の感情を整えるステップ
「やりなさい」と言いたくなる。 「どうしてやらないの!?」と怒りたくなる。 そう感じるときは、親側の感情が大きく揺れている証拠でもあります。
「子どもに期待すること自体は悪いことではない。
でも、それを“押し付け”にしないためには、自分の願いを“言語化”することが大切です」
あおいさんは、自分がどんな“願い”を持っているのか、紙に書き出していったといいます。
「私はこの子にこうなってほしいと思ってる」「こうしてほしいと願ってる」——。
その願いが強すぎると、「やりなさい」が出てしまう。
「感情をコントロールするには、自分の“願いの正体”に気づくこと。
これは時間がかかるけど、いちばん確実な方法だと思います」
■「やる気がないように見える」は誤解かも?
「どうせうちの子はやる気がないから…」
そんなふうに見えてしまうとき、実は大人側の“見方”に偏りがあるのかもしれません。
「やる気がないように見えるだけで、本人の中には別の感情があるかもしれない。」
目立った行動がないだけで、内側では葛藤していたり、準備をしていたりする可能性も。 子どもの内面は、見た目だけでは判断できません。
「やる気がなく見えることより、もっと良いところを見つけていく。
子どものいろんな面を見てスポットライトを当ててあげると良い面が見えてきたり、立体的にその人を見ることができるんです」
■“やりたい”を引き出すためにできること
チャイルドコーチングにおける「やる気の引き出し方」は、スキルよりも“あり方”が土台です。
「コーチングの影響力の9割は、“どんな人が言うか”という土台だと言われています」
土台が整っていれば、子どもを見る目も自然と変わる。
親が子どもに対して「あなたってすごい人だよね」と思えているか。その“まなざし”が、子どものセルフイメージに直結します。
そして、自分の良いところを伝えられることで、子どもは「僕って価値があるんだ」と実感し、自己肯定感が育っていきます。

■親としての「NG」はあるの?
最後に「やってはいけないこと」についても尋ねてみました。
「“これを言ってはいけない”というNGワードはあまりないと思っていて。
親だって叱ることもあるし、それでいいと思うんです」
ただし注意したいのは、「子どもの人格をジャッジする言葉」。
「あなたはいい子、悪い子」「どっちが正しい、間違っている」——。こうした親の采配のジャッジは、子どもの反発や、やる気を失います。
「“私はこう思うよ。あなたはそう思ったんだね。両方OKだよ”
そんなフラットな関わりができるよう、日々意識しています」
■さいごに
子どもに「自分で動ける力」を育てたい。
そう願うすべての親に、あおいさんはこう語ります。
「やる気って、スキルじゃなくて、“信頼の土台”から育つもの。
子どもの“やりたい”を引き出すには、まず“親が信じること”から始まると思います」
毎日、完璧にできなくてもいい。
ただ、子どもを一人の人として尊重し、良いところを見つけて伝えていくこと。
その小さな積み重ねが、子どもの自己肯定感を育み、「やってみたい!」につながっていく。
信頼関係という土台を育みながら、今日から10分、子どもと“本当に向き合う時間”を持ってみませんか?
.png)
あおいさん
チャイルドコーチングを通じて「子どもの“やりたい”を引き出す」子育てを提唱。
長男の幼少期、自身の“やらせたい育児”に違和感を覚え、チャイルドコーチングと出会う。
現在は、アドラー心理学を取り入れたコーチングでオンライン講座やSNSで親子関係のヒントを発信している。
Instagram:@aoi_coaching_kosodate
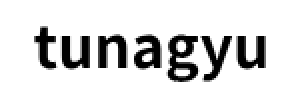

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 247
閲覧数: 247
 閲覧数: 230
閲覧数: 230
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204