── 偏食カウンセラー・ゆうこ先生インタビュー
あなたのお子さんは「白ごはんしか食べない」「トマトしか食べない」…そんな“極端な偏食”に悩んでいませんか?
確かに、子どもがごはんを食べてくれないと、栄養や成長への不安は大きくなります。SNSでは「偏食は親のせい」といったプレッシャーもあって、ますます自分を責めてしまうママも多いのではないでしょうか。
でも実は、偏食には理由があり、「アプローチの仕方」を変えるだけで、子どももママもずいぶんラクになるんです。
今回は、Instagramで「偏食カウンセラー」として発信し続けるゆうこさんに、極端な偏食と向き合うための考え方や、日常でできる工夫について伺いました。
■知識があっても、つらかった。だから「ママ」に寄り添いたい
偏食カウンセラーのゆうこさんは、3人の男の子のママ。栄養学の博士号を持ち、長年管理栄養士として活動してきた彼女でも、育児の壁にぶつかったといいます。
「下の双子に発達特性があって、とにかく全然食べなかったんです。
癇癪もすごくて…知識があるからこそ“ここだけは食べてほしい”と願って、余計に苦しくなっていました」
SNSで目にした療育センターの知見や、会食恐怖症の当事者による発信に共感し、少しずつ偏食に向き合う方法を学びました。
でも、どれだけ正しい知識を持っていても、日々の食事で消耗してしまう現実は変わりませんでした。
「その家庭でできる方法を一緒に探しながら良い方法を見つけたかった。
偏食で悩んでいたり、理解されないママに寄り添いたい気持ちを強く持っていました。」

■極端な偏食、背景には“感覚”と“記憶”がある
ゆうこさんによれば、極端な偏食には発達特性や感覚過敏、過去の食体験などが関係していることが多いといいます。
「たとえば“コロッケの衣が針のように見える”“葉っぱの葉脈が気持ち悪い”など、私たちとは違う世界を子どもが見ていることもあります」
また、偏食の子は記憶力が高く、「この見た目の料理=この味」と強く覚えていることがあるため、いつもと味が違うだけで拒否反応が出ることも。
■“無理に食べさせる”が、偏食を深刻にする?
「せめて一口だけでも」と思うのが親心。でも、それが逆効果になるケースは少なくありません。
「“食べさせたいママ”VS“食べたくない子ども”という構図になると、食事が“戦い”になってしまうんです」
ゆうこさんは、親子を「対立」から「チーム」に変えることを提案します。
「“このごはんはなぜ食べられないんだろう?”って、一緒に考え立ち向かう“チーム”になってみてください」
そして、幼少期の食育でもっとも大切なのは、「食べることは楽しい」「ごはんの時間が楽しみ」と思える気持ちを育てていくことだと、ゆうこさんは言います。
「今は食べられるものが少なくても、“食事って楽しい”という気持ちがあれば、必ず食べられるものは増えていきます。
ずっと“できないね”と言われ続けると、『ぼくは食べることが苦手な人間なんだ』と感じてしまうこともある。
そんなふうに自尊心が傷ついてしまうのは、とてももったいないことなんです」

■“食べる”はゴールじゃない。小さな前進を見逃さないで
偏食の子は、「見る」「匂いをかぐ」「触る」など、食べるまでにたくさんのステップを必要とします。
「今日はにおいをかげた、口に入れてみた、でも出しちゃった…それでもすごい進歩なんです」
ゆうこさん自身も、2週間毎日バナナを口から出し続けた息子が、ある日突然飲み込めて大好物になった経験があるそう。
出すための専用の容器を用意して、「出してもいいよ」と伝えるだけで、子どもが“挑戦できる場”になります。
■家庭でできる声かけと工夫
まずは、子どもの「好きな食べ物・特に苦手な食べ物」を書き出し、食感・温度・水分量などの子どもの好みの傾向を分析。
「たとえばカリカリ食感が好きな子は、煮物が苦手な傾向があります。
また、"お子さんが好きな味や食感をイメージできる"説明・声掛けをしてあげると、食べられる可能性が高まるんです」
さらに、「これは〇〇ちゃんの好きな唐揚げに似てるよ」と具体的に伝えることで、子どもの想像力を助け、ひと口のハードルが下がります。
■サプリより“成長曲線”。SNSに振り回されないで
「栄養が足りていないかも」と不安になるママに対しては、まず“成長曲線”を見てほしいと話します。
「背が伸びて、体重も増えているなら、とれている栄養もあるということ。
サプリをとりすぎて逆に便秘になるケースもあります」
SNSで「偏食=鉄分サプリを」といった情報が流れても、それが本当に必要かは一人ひとり異なる。目の前の子どもを“よく観察する”ことの方がずっと大切だといいます。

■“今”向き合うことで、思春期もきっとラクになる
ゆうこさんは、子どもが小学生になる前と、特に「3年生くらいまで」がターニングポイントだと考えています。
「思春期に入ると、どんどん親と距離ができていきます。
だからこそ、幼少期に“ママはわかってくれる”という信頼を育んでおくと、その後が違うんです」
偏食は、ただの「困りごと」ではなく、「子どもとしっかり向き合えるチャンス」だと語るゆうこさん。
「わがままだな、頑固だなって思うその部分が、実はその子の個性かもしれない。
まずは“どうして食べないのかな?”って考えてみて欲しいです」
そして、その子の目で世界をのぞいてみてください。
■さいごに
偏食は、“誰かが悪い”から起きているわけではありません。子どもには、子どもなりの“食べられない理由”があって、それを一緒に見つけていくプロセスにこそ意味があるのです。
大事なのは、今食べられるものを大切にしながら、子ども自身が「食べてみようかな」と思える環境を整えていくこと。
今回のお話の中で、ひとつでも「やってみようかな」と思えたことがあれば、ぜひ試してみてください。
食事の時間が、“不安”から“安心”へと変わるその一歩を、応援しています。
.png)
ゆうこ先生
管理栄養士・食品栄養科学博士。三児の母。
長男と双子の息子の子育てを通じて「発達特性と偏食」に向き合い、Instagramで“子どもとママの心に寄り添う偏食支援”を発信中。
「無理に食べさせるのではなく、子どもが自ら食べたくなる環境づくり」を大切にし、栄養の視点と感情ケアの両面からサポートを行っている。
子どもの偏食に悩むママたちが「気持ちがラクになった」と感じられるよう、実体験に基づいたアドバイスを日々届けている。
ゆうこ先生の詳しい情報はこちらから
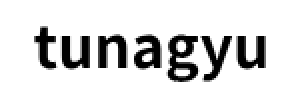

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 255
閲覧数: 255
 閲覧数: 246
閲覧数: 246
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204