── イライラママを笑顔に導く専門家・アリスさんインタビュー
きょうだいゲンカ。何度止めても、また始まる。
「今度こそ仲良くしてくれるかも」と願っても、気づけばどちらかが泣いていて、気づけばママがまた怒鳴ってしまう——。
あなたもそんなループに心当たりはありませんか?
実は、きょうだいゲンカには「見守る」ことでしか育たない力があります。そして、イライラを減らすためには“止め方”よりも、“関わり方”の見直しが効果的なのです。
今回は、イライラママを笑顔に変える専門家として活動するアリスさんに、「きょうだいゲンカ」について詳しくお話を伺いました。
■きょうだいゲンカは“人間関係の練習”
「「私は、きょうだいゲンカは“人間関係を学ぶ大切な練習の場”だと思っています」
そう語るアリスさん。つい親としては「また始まった…」とため息をついてしまいがちですが、アリスさんの視点はまったく違います。
「感情をどう表現するか、相手の気持ちをどう想像して折り合いをつけるか、思い通りにならない経験をどう乗り越えるか…。
これって、大人になっても必ず必要なスキルですよね。家庭という安全基地で、きょうだいを相手に練習していると考えています」

■止める?止めない?介入のタイミング
アリスさんは基本的に「すぐには止めない派」。
ただし、これは「放置」とはまったく違います。
「怪我につながりそうなときや、叩く勢いが強くなったときには、間に入ります。
でも“じゃれてるだけ”のような場面では、黙って様子を見るようにしています」
たとえば弟が電車のおもちゃで叩こうとしたら即ストップ。兄弟の体格差を考慮して、力加減によってはすぐ介入する。
でも、すぐ怒鳴ったり「どっちが悪いの!?」と責めたりはしない。
■「親はジャッジしなくていい」
きょうだいゲンカでよくあるのが、「どっちが悪いか分からない」問題。
そんな時、親は“審判”になる必要があるのでしょうか?
「私は、どちらかを“悪者”にしなくてもいいと思っています。
親はジャッジじゃなくて、中立の立場で両者の気持ちに共感して、代弁してあげるのが理想的です」
「お兄ちゃんはこうしたかったんだね」「弟くんはこうしてほしかったんだね」と、お互いの気持ちを整理して伝える。
そのうえで、「こういうやり方ならどう?」と代替案を提示する。アリスさんは、そんな“対話のサポーター”として関わっています。
■叱ること=悪ではない
「とりあえず怒ってしまう」というママも多いもの。
でもアリスさんは、それを責めません。
「私も長男が小さいときは怒鳴っていました。それだけ子どものことを思っている証拠だと思います」
個性心理學の視点からも、「兄弟ゲンカにイライラしやすい」傾向があるといいます。たとえば“人を大事にするグループ”の人は、子ども同士の感情のぶつかり合いを“かわいそう”と感じやすいそう。
怒ってしまうのは、「ルールが守られていない」「声が大きすぎる」といった自分の価値観に反するからかもしれない。
まずは「自分が何にイライラしているか」に気づくことが大切だといいます。

■“気持ちを言葉にする”サポートを
アリスさんが大切にしているのは、「気持ちを言葉にする」サポートです。
「長男は自分の気持ちを言葉で表現するのが苦手だったので、
私が“これが嫌だったの?”“こういう気持ちだったの?”と代弁してあげていました」
感情の言語化は、けんかの“中”だけでなく“後”にも必要。
「叩くのはダメ」だけで終わらせず、「叩きたくなるくらい嫌だったんだね」「次は言葉で伝えてみようか」と、気持ちを整理しながら次の行動を導いていきます。
■きょうだいそれぞれの“個性”を理解する
個性心理學で見るとアリスさんのご家庭の長男は“1人で過ごしたいペガサス”、次男は“誰かと一緒にいたいひつじ”。まったく正反対のタイプ。
「次男が一緒にいたくて長男の部屋に入っちゃう。それでケンカになることが多いんです。
でも、“にぃにと一緒にいたかったんだよね”“でもお兄ちゃんは1人で過ごしたいんだって”と気持ちを整理して、次男には“じゃあママと一緒にテレビ見ようか”と代替案を出すようにしています」
無理に説得せず、タイミングをずらして再交渉することも。
大事なのは「押しつけないこと」だといいます。
■子ども同士の“解決力”は育てられる
アリスさんは、子どもが自分たちで解決できる力も“育てていくもの”だと話します。
「1つは“自分の気持ちを伝える力”、2つ目は“相手の気持ちを想像する力”、3つ目は“仲直りの方法”。
この3つを親が少しずつ教えてあげることで、子どもは学んでいけると思います」
はじめは親が代弁したり、選択肢を与えたりしながら、
「こうすればうまくいくんだな」という知識が子どもの中にストックされていく。
それが、将来の対人関係力を支える土台になります。

■「叱りすぎたかも…」そんなときのリセット法
つい片方だけを叱ってしまった。そんなときも、後からのフォローが大事。
「“我慢してくれてありがとう”“優しくしてくれたね”と声をかけたり、“叩いた行動がダメだったけど、あなたのことは嫌いじゃない”と伝えてあげることで、自己肯定感を守ることができます」
行動を否定しても、人格まで否定しない。
その違いをきちんと伝えることで、子どもも安心します。
■きょうだいゲンカを通して、育つ力
アリスさんは、きょうだいゲンカを通して「5つの力」が育つといいます。
感情をコントロールする力
交渉する力
思いやり
問題解決力
自己主張と妥協のバランス
きょうだいゲンカ=悪いこと”とラベリングせず、“育ちの場”と捉えることで、親も少し気持ちが軽くなります。
■さいごに
つい止めたくなる。つい怒ってしまう。
そんなきょうだいゲンカに、あなたも日々振り回されているかもしれません。
でも、きょうだいゲンカは“人間関係を学ぶ大切な場”であり、“感情のトレーニング”でもあります。
親ができるのは、叱るのでも、放置するのでもなく、「見守る」こと。そして「タイミングよく寄り添う」こと。
アリスさんの実践のように、子どもたちの個性に合わせた関わり方を見つけていくことで、
きょうだいゲンカは「成長のチャンス」に変わっていきます。
.png)
アリスさん
「イライラママを笑顔に導く専門家」として活動中。
個性心理學の認定講師・カウンセラーとして、親子の“思考のクセ”と“個性の違い”を軸に、ママの子育てサポートを提供。
過去には自身も「押し付ける育児」に悩み、葛藤の末に心理学を学び始める。
現在はInstagramを中心に、オンライン講座・相談を通じて多くのママに寄り添っている。
アリスさんの詳しい情報はこちらから
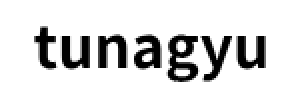

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 255
閲覧数: 255
 閲覧数: 246
閲覧数: 246
 閲覧数: 230
閲覧数: 230
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204