── ともこ先生インタビュー
あなたは、子どもに「もっと自分で考えて動いてほしい」と思ったことはありませんか?
確かに、自分で判断し行動できる力は、これからの時代に欠かせない力です。実際、保護者の7割以上が「子どもの思考力・判断力を育てたい」と考えているという調査結果もあります(ベネッセ教育総合研究所)。
でもその一方で、「つい先回りして指示してしまう」「考える時間がなくて全部やってしまう」といった悩みもよく聞かれます。
“自分で考える力”は、言葉で教えて育つものではありません。日常のささいなやりとりや、小さな選択の積み重ねの中で、少しずつ育っていくものなのです。
今回は、12年間の保育士経験と現場の声を活かし、非認知能力を育む子育てを発信する「ともこ先生」に、考える力の育て方や親のあり方についてたっぷりとお話を伺いました。
■「非認知能力」を育てることが、未来を生きる力につながる
ともこ先生は、現在オンラインとリアル両面で、非認知能力=「考える力」「人間力」「生きていく力」を育む子育てをテーマに活動中。保育士としての経験を活かしながら、ママたちと対話を重ね、講座や発信を続けています。
「“考える力”って、抽象的に聞こえるかもしれないけど、結局は“自分とどれだけ仲良くなれるか”が鍵なんです」
自分が何を感じ、どうしたいのかを日々キャッチすること。その積み重ねが、自分の考えを持ち、伝える力につながっていくのだと語ります。
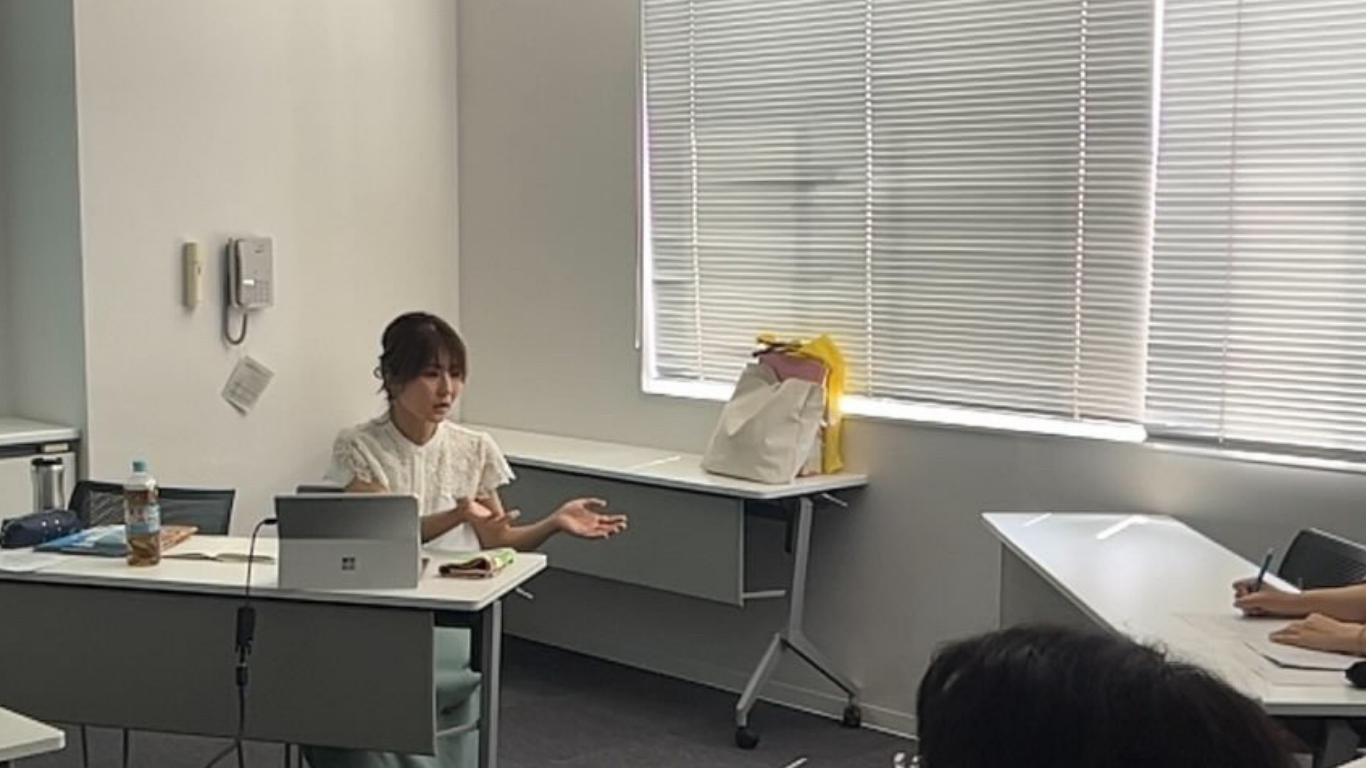
■選ぶ体験・意見を尊重される体験が、土台をつくる
幼少期に考える力を育むには、具体的にどうすれば良いのでしょうか?
「“どっちがいい?”って選ばせる機会や、“あなたはそう思ったんだね”って意見を受けとめることが大事なんです」
例えば、ランドセル選びで本当は水色がよかったのに親に却下された子がいた。その後、妹は好きな色を選べた。小さな“否定される経験”が、子どもの思考や選択への自信を奪うこともあるのだと話します。
「あなたの意見には価値がある」
その感覚を、小さな“選ぶ”や“認めてもらう”経験から育んでいくことが、自己信頼と考える力のベースになります。
■“いきなり考える”はできない。だからこそ幼少期の積み重ねを
子どもが小学校高学年になると、「自分で考えて行動してほしい」「言われなくても判断してほしい」と親が願う場面が一気に増えてきます。
しかし——
「それまで“考える経験”を積んできていなかった子は、いきなり“自分で考えて”と言われてもどうしたらいいかわからないんです」
今までは“こうしなさい”って言われてやってきたから、自分の気持ちがわからない。“どっちがいい?”って聞かれても、答えられない。そんな子どもたちも少なくはないのだそうです。
だからこそ、「小さいうちから」がカギ。
「どっちがいい?」「どう思う?」と日々問いかけ、子どもの中に“自分の意見”という種をまく。
その積み重ねこそが、将来「自分の頭で考えて進む力」につながっていくのです。
■「たくさん話して、たくさん聞く」——日常会話こそが“思考のトレーニング”
子どもに考える力を育んでほしい——そう願うなら、まずは日々の会話の中で“相談ベース”のやりとりを意識することがおすすめだと、ともこ先生は語ります。
“これどう思う?”“こっちがいいかな?”というように、大人の悩みをあえて子どもに相談します。すると、子どもはちゃんと考えて相談に答えてくれます。
「親が“上の立場から聞く”のではなく、“対等な一個人”として向き合う姿勢」
そこには上下関係ではなく、信頼と尊重の“フラットな関係”が生まれます。
「そもそも、相談するということは 『この人なら信頼できる』と思っているから。
逆に、信頼していない人には相談しないものです。
子どもは言葉でははっきり言わなくても、そういう“信頼されている感覚”を敏感に感じていると思うんです」
“話しやすい、信頼のある環境”を家庭の中に作っておくこと。
それこそが、子どもが「自分の考えを持ってもいい」「聞いてもらえる存在なんだ」と感じられる、最初のステップになるのです。

■口答えや反発は“考えている証拠”
「うちの子、口ごたえが多くて……」
そんな悩みも、実は成長の証かもしれません。
「親の意見に“それはイヤ”と言うのは、自分の意見を持っている証拠。
反発というより、“違い”があるというだけ」
だからこそ、「なんでそう思うの?」と問いかけたり、「あなたはそう感じたんだね」と受けとめることが大切です。
■時間がないときは“無理”でいい——信頼の貯金が大事
「本当は考えさせたいけど、忙しくて余裕がない」という悩みも多いもの。
「全部やろうとしなくていいんです。時間がないときは“ごめん、今は無理”でOK。
大事なのは、余裕があるときにどれだけ関わっておくか」
ふだんの小さな対話や選択の経験が、“信頼の貯金”になります。
たとえば道を選ばせる、服を選ばせる、小さなことでOK。その言葉と実践が、子どもの信頼を積み上げます。
■失敗を恐れない。“自分で気づく力”を信じる
「忘れ物をさせないように、つい全部チェックしてしまう」という親心にも、こう答えます。
「失敗って“学びの機会”なんですよ。
忘れ物をして、先生や友達に助けてもらって、ありがたさに気づいたり、自分でどうするかを考えるきっかけになったりする」
大人が先回りして防いでしまうことで、子どもは“気づく力”や“頼る力”を得る機会を奪われてしまうのです。
忘れ物をして困った子は、次から工夫するようになります。そこには、親が与える以上の“自分で考える力”が育っています。

■子どもの考える力を育てるため重要なのは親の“質問力”
「自分で考える力」を育てるには、実は“質問”の仕方がとても大切だと、ともこ先生は語ります。
「教えるベースではなく、問いかけで本人が考えて答えを出すように導いていく質問がとても大事なんです」
たとえば、子どもがケンカして帰ってきたとき——
「何があったの?」「あなたはどう思った?」「どうしたかったの?」と聞くことで、子どもは自分の気持ちを“言葉”にしようとします。これは、頭の中で考える訓練そのもの。
一方で、「なんでそんなことしたの!」「ちゃんと謝ったの?」と聞かれてしまうと、思考よりも“正解探し”になってしまうのです。
何があった?→事実確認
どうしてだと思う?→問題提起
どうしたらいいと思う?どうしたい?→未来に向けて
大人が「教える人」になるのではなく、「問いかける人」になること。
子どもが自分の気持ちや考えに気づき、それを言葉にする過程を支えることで、自然と“考える力”は育っていきます。
■子どもの考える力を引き出すカギは、ママの“自己肯定感”
子どもに“考える力”を育てたいなら、まずはママ自身が“自分の気持ち”に目を向け、自分自身に問いかけることが大切です。
ともこ先生は、そうした姿勢の土台にあるのが「自己肯定感」だと語ります。
「お母さんって、どうしても子どもや家族のことを優先して、“自分を後回し”にしがち。
でも本当は、“私って今どう感じてる?”“どうしたかった?”と、自分に問いを持つことがすごく大事なんです」
この“自分に集中する時間”こそが、ママの自己肯定感を高める第一歩。そして、それはやがて子どもの自己肯定感にもつながっていきます。
「ママ自身の自己肯定感を高めることで、子どもに良い質問をアシストしてあげれると信じています。」
“考える力”を育てる前に、“考えられる心の土台”を育てていく。ともこ先生は、そんな親の在り方こそが子どもの未来をつくると信じています。
■さいごに
「自分で考える力を育てたい」
そう思ったとき、つい“教える”ことに意識が向いてしまうかもしれません。
でも実は、子どもが自分で考えられるようになるために大切なのは、“意見を尊重される体験”と“自分で選ぶ機会”の積み重ね。
それを支えるには、親自身が「見守る余白」を持つことも欠かせません。
まずは、今できるところから。「今日は選ばせてみよう」——その一歩が、未来の自立、考える力につながります。
.png)
ともこ先生
12年間の保育士経験を活かし、非認知能力(考える力・人間力)を育てる子育ての実践と発信を行う。
オンライン・リアル両方でママたちとの対話を重ねながら、講座や講演、ラジオでの情報発信を精力的に展開。
「ママ育てから始める子どもの人間力をぐんぐん伸ばすともこ先生メソッド」を発信し、親子で育ち合う子育てを応援している。
ともこ先生の詳しい情報はこちらから
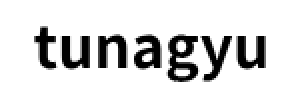

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 255
閲覧数: 255
 閲覧数: 246
閲覧数: 246
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204