── 先生夫婦のママ先生・あきさんインタビュー
あなたのご家庭では、「片づけに移れない」「宿題のスイッチが入らない」「寝る前に高ぶってしまう」——そんな子どもの“切り替えの壁”を感じたことはありませんか?
実は音楽は、その壁をやわらかく越えるための頼もしいツール。テンポやメロディ、合図としての“音”を暮らしに少し添えるだけで、子どもの「できた」が増えていきます。
今回は、小学校の担任・音楽専科・巡回指導教員(通級)・特別支援学級と現場を歩み、現在は発達凸凹キッズのための音楽教室づくりにも取り組むあきさんに、学びと暮らしをラクにする「音楽×習慣づくり」のコツを伺いました。
■「先生」と「ママ」の両方を歩いた等身大の視点
あきさんは担任を約8年、その後は音楽専科として教科指導や合唱や式典の指揮を担当。ルーツは幼少期からのピアノ、中学の吹奏楽、大学での声楽・合唱団指揮という“音の人”です。
一方、中度の知的障害と自閉症がある息子さんが小1に上がったとき“小1の壁”に直面。「息子も荒れて私も荒れて」教員をいったん退職し、働き方をかえて巡回指導教員を2年間担当。
今年は特別支援学級の音楽、書写などの教科指導に加えて、通常学級の音楽、英語も受け持つ“マルチ教員”。午前は学校、午後は発達凸凹ちゃんのための音楽教室の準備・運営へ。
「お母さんが孤独になることがすごく多くって……心のケアができる場所を作りたい」
現場と自宅、両方で重ねた工夫を、親子の毎日に使える形にして発信しています。
■音楽は“ことばの前のことば”——つながりを作る共通言語
指示や禁止を“声量”で伝える代わりに、リズムにのせた短いフレーズで届けるのがあきさん流。
「『だめだよ』って言うんじゃなくて、音楽のフレーズを使って“今はだめ♪”みたいに可愛い感じで。
ジェスチャーも入れると、結構みんなストンって入ります」
また、幼児期の手遊び歌も立派な土台。「とんとんとんとん ひげじいさん」の一定リズムに“心地よさ”を感じられることが、違いに気づく感覚へ、やがて学びへとつながっていきます。
■リズムは学びの下地——九九も体育も“テンポ”でラクに
「九九は一定の拍で唱えると覚えやすく、取り出しやすい」と、学習に音楽を取り入れるメリットも教えてもらいました。
「スピードは段階的に。ゆっくりだとテストもゆっくりになっちゃうので、だんだん“アテンポ”にしていく——
処理速度を無理なく育て、計算がはやくなっていくことにも繋がっていくんです」
体育でも、陸上なら【位置について、よーい、どん】。跳び箱なら【どん(踏み切り)→ばん(手をつく)→とん(押して飛ぶ)】と身体の動きとリズムをマッチングさせると動きが安定します。
■発語が出にくい子には“うたマッチング”——物と言葉をメロディで結ぶ
言葉が出にくい子には、もの+音+ことばをセットにして、自然に楽しくしみこむように伝えるのがおすすめです。
「『バラ』のカードを見せながら〈バ・ラ/バ・ラ〉って2拍で歌うと、発語が難しいお子さんが急に『バラ、バラ』って言ってくれたりするんです」
調や音の高さに決まりはありません。ママとお子さんのやり取りの中で、心地いい高さを選べば大丈夫。いま気になっている物(たとえば「スマホ、スマホ」など)に小さなフレーズを添えると、物と言葉が自然とつながっていきます。

■“曲タイマー”で切り替え上手に
切り替えが上手くいかないときは、まず音で見通しをつくってみましょう。
家庭なら、子どもが選んだ好きな曲を「片づけ曲」に決めて、流れているあいだは片づけに集中——曲が終わったらおしまいという約束にしておくと、時間が耳でわかるので動きやすくなります。
宿題へ移る前も、子どもが選んだ好きな曲を「準備の合図」にしておくと、「この曲が鳴ったら筆箱とプリントを出す→イスに座る」のように動作と結びつけやすく、毎回くどくど説明しなくても自然と体が動きます。
曲の長さ自体が小さなタイマーになって、子どもが自分で切り替えのリズムをつかみやすくなります。
またきょうだいの順番交代や家庭内の役割チェンジも、リズムにのせた短いフレーズを“合図”にすればスムーズ。
「低学年の内に“音で動く”を習慣化して、そこから“言葉で動く”に変えていく。
最終的には自立につながります」
■寝る前はBPMを落とす——音と光でスイッチをオフ
就寝前は、アップテンポ→ゆっくりへ。 その音楽と合わせて照明をオレンジ系に変えてあげるのがおすすめです。
「好きな曲を“切り替えの音楽”みたいに決めて、なったらおしまい。
耳は最後まで働くから、音でリセットできます」
また興奮が強いときは、毛布をパサッとかける、電気を消す、静かな音など、落ち着くセットを準備しておくと安心です。
■“選ぶ”は自己肯定感の練習——2択→3択→自分で1曲
「お母さんが全部選んでやってあげると受動になっちゃうんです」
だからこそ、はじめはAかBの二者選択、次に三者選択へと広げ、ゆくゆくは一曲を自分で選ぶところまで段階を踏みます。
自分で決めて、その選択で眠れたという経験が積み重なるほど、「できた」「満足した」という小さな自己実現が育ちます。
さらに、きょうだいと一緒に選ぶ日は“多者意識”が育ち、自然と社会性の練習にもつながります。

■まずは“手拍子”から——真似っこが集中力と板書力に効く
最初の一歩はシンプルでOKです。
「お母さんが手を1回叩いたら1回、3回叩いたら3回。
『腕まくりするね』って言って一緒にやる——この“マネる”はすごく大事」
視線→ワーキングメモリ→短期記憶→手指の操作という流れを自然に練習でき、小学生になったときのノートを写す力、集中力にもつながります。
■さいごに
実は、特別な準備がなくても、私たちはもう日々の暮らしの中で音楽の力を使えています。手拍子で呼びかけたり、鼻歌で気分を切り替えたり、名前を呼ぶ声に少し抑揚を添えたり——そんなひと工夫だけでも、“できた!”へ向かう小さなエンジンになります。
また、音楽は次に何をするかの合図になり(見通しづくり)、くり返しはその場で覚えておく短期記憶をそっと助け、テンポは心と体のスイッチをやさしく切り替えてくれます。
だからこそ、感覚や切り替えがゆっくりな発達凸凹キッズにとって、音楽は「がんばれ」と急かすものではなく、「だいじょうぶ、一緒にいこうね」と寄り添うやさしいサポーター。日々の暮らしに少し添えるだけで、親子の歩幅はやわらかく整います。音楽はいつでも近くにあって、あなたの育児の味方です。
まずは、今日できそうなことをひとつだけで大丈夫。できた瞬間に気づいたら、親子で拍手をひとつ。そんな素敵な前進を、これからもいっしょに、やさしく重ねていきましょう。
.png)
先生夫婦のママ先生・あきさん
小学校担任→音楽専科を経て、巡回指導教員(通級)・特別支援学級で指導。午前は学校で複数学年・教科を担当、午後は発達凸凹キッズのための音楽教室を準備・運営中。中度知的障害・自閉症の息子の子育て経験をベースに、“家庭と学校のすきま”を専門的にサポート。
「特別支援を特別にしない社会をつくりたい」という発信にてBEAUTY JAPAN SAITAMA2025 グランプリを受賞。BEAUTY JAPAN 日本大会2025 グランドファイナリストとして挑戦中。
Instagram: @sin_sensei_fufu
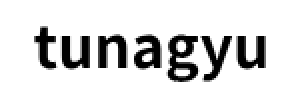

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 245
閲覧数: 245
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 204
閲覧数: 204