——森久保 智香さんインタビュー
あなたは、朝の支度や園・学校での様子を見て、つい声が厳しくなっていませんか? 確かに、きょうだいとの違いや周りの視線を感じると、不安で胸がぎゅっとなりますよね。
結果、「この育て方で合っているのかな」と答えを探し続けて疲れてしまい、親子ともに毎日が少し息苦しくなることも多いと思います。
でも実は、子どもの特性に合わせて環境を少し整え、声かけや伝え方を少し見直すだけで、親子の呼吸はぐっと楽になるんです。
そこで今回は、次男の特性をきっかけに学び直し、ママたちに伴走している森久保智香さんに、発達特性のある子の子育てで大切にしたいことを伺いました。
■手放して、はじめて見えた道
森久保さんは中2の長男・小4の次男のママ。次男くんは軽度の知的障害があり、地域小学校の支援級に在籍しています。
フルタイムで働くワーママを卒業し、次男のサポートをきっかけに学び直しへ。今は講座と長期のマンツーマンサポートで、発達に悩むママたちに寄り添っています。
「本当に仕事が好きで続けていましたが、次男の遅れがわかったとき『今できるのは家庭に入ること』と感じ、退職を決めました」
さらに、知的・聴覚障害のある弟さんの存在も活動の原点に。「兄弟児・親、両方の視点が分かる」強みを生かし、当事者家族の揺れに寄り添う発信を続けています。

■きっかけ——仕事を手放し、家庭へ
次男くんは、年中のころに発達の遅れを指摘されました。療育・支援センターを勧められるも、コロナ禍+フルタイムで余白ゼロ。
「始めは、次男のサポートっていうところで仕事を離れたんですよね。
次男と向き合うほど、わからないことも見えて不安を感じるようになり、そこで自分から情報を集めて学び始めました」
負けず嫌いの性格に背中を押され、「このつらさをこのままで終わらせたくない」という思いが森久保さんを前へ進ませました。やがて「同じ悩みを持つママにも役立てたい」と考え、情報を受け取る側から発信する側へと踏み出しました。
■生きづらさの正体——特性×環境のミスマッチ
「診断の有無に関わらず、誰にでも特性があります。生きづらさになるか強みになるかは“環境次第”」
感覚の過敏さや関わり方の好み、理解の進み方は人それぞれ。それでも現場では「みんな同じ」を前提に動く場面が少なくありません。森久保さんは、次男の子育てを通じてそのギャップに気づき、違和感を覚えるようになったと話します。
その結果、親は「自分だけ我慢すればいい」「どうせ理解されない」と抱え込み、子どもを既存の枠に当てはめたり、不向きな環境でがんばり続けてしまうこともあります。
そうなると少しずつしんどさが積もってしまうので、必要なことを周囲に少しずつ共有していくことが大切です。最初の小さな一歩の共有が、互いの理解を育てるはじまりになります。
■本人のしんどさと周囲の“困りごと”のギャップ
「『落ち着きなさい』『こうしなさい』と言われてできるものではない。
本人は不安や恐怖を抱えているのに、周りには“わがまま”に見える——そのギャップがつらい」
心の中では不安や怖さ、「どうしたらいいかわからない」という気持ちを抱えていることが多いのに、周りからはわがままに見えたり、落ち着きがないように映ってしまう。
その結果、「困っている本人」と「困らされていると感じる周囲」の間にギャップが生まれます。
「知らないことは誰にとっても不安。
だから“知る”を増やす歩み寄りが大切です」
良し悪しで急いでジャッジする前に、互いの「知らない」を埋めることが大切です。
保護者は特性や必要な配慮を先生や周囲に共有し、周囲は学びを重ねて理解を深めていく。違いは当たり前で、関わりを豊かにしてくれるもの——
その前提に立てると、共通点も見つけやすくなり、「自分に置き換えるとこう感じるのかも」と想像が広がり、誤解はぐっと減ります。
こうした小さな歩み寄りの積み重ねが、ギャップを少しずつ縮めていきます。

■家庭は“安心の基地”にする
「家庭はまず、子どもにとって『安心できる場所』であってほしい——これが大前提です」
安心が土台にあるからこそ、子どもは新しいことに挑戦できます。やり方やノウハウは子どもによって違いますし、情報も道具も今はたくさんあります(見通しを示す視覚ツールなど)。
それでも一番の基礎は「家が安心な場所であること」。そのためには、私たち大人自身が安心して過ごせる環境を整えることも欠かせません。
「具体的には『あなたはあなたのままでいい』と受け入れられている感覚」
親が本心でそう思えていないと、子どもにそのメッセージは届きません。だからこそ、親子ともに“そのままを認め合える”安心感を育てていきたいですね。
■自己肯定感を守る声かけ
「『すごいね』『えらいね』は私の主観。結果より過程を言葉にします」
声かけは「すごいね」「えらいね」のような評価は言いやすく、つい使いがち。ですが、過程と事実を伝えるのがポイント。
たとえば「ここまで自分でやったね」「さっきはこう工夫してたね」「いま静かに待てているね」など、取り組みや状況をそのまま言葉にして「見ているよ」を届けるイメージで伝えてあげます。
結果だけでなく歩みを認めることで、子どもは「分かってもらえた」と感じ、自己肯定感が育ちます。また年齢に合わせて、短く具体的に伝えるのもコツです。
■感謝と要望をセットにして
先生や学校、放課後等デイなど多くの機関と関わるほど、子どもにはさまざまな視点が加わり育ちが豊かになります。だからこそまずは関わってくださる方への感謝を土台にできたら素敵ですね。
「関わってくれる人への感謝がベース。
でも、伝えたいことは我慢しない。感謝と要望はセットで伝えます」
そのうえで、「言いづらいから黙っておく」ではなく、感謝と要望をセットで、やわらかく共有していくことが大切です。お互いに本音が言えない関係は、いずれストレスになってしまいます。
「『家庭でやる』『学校にお願いする』を線引きします。
家庭でしんどい部分は、先生から伝えてもらう方が届くこともあります」
また、役割分担を意識することも重要です。保護者が抱え込みすぎない、でも学校に丸投げもしない。「ここは家庭で取り組む」「ここは先生にお願いしたほうが子どもに届きやすい」と線引きをし、子ども中心で決めていくと、風通しのよい連携が続いていきます。

■疲れはサイン。休む・頼る・手放すを選ぼう
「休む、誰かとつながる、好きなことをやる、手放す——正解・不正解はありません。無理しているときに疲れはたまります」
疲れ方は人それぞれ。だからこそ、まずは今の自分が何を必要としているかにそっと目を向けてみてください。発達特性のある子の子育ては、程度にかかわらず本当にがんばりのいること。
体がつらいならしっかり休む。心がしんどいなら誰かに話を聞いてもらう、同じ立場の人とつながる。我慢が続いているなら好きなことを思い切りやる。抱え込みすぎているなら手放す。
「〜すべき」「〜ねば」から一歩離れて、本音に忠実に選んでいいんです。
疲れているのは無理を重ねているサイン。正解・不正解はありません。今の自分に合うケアを、あなたのペースで選んでいきましょう。
■さいごに
その子だからこそ出会える景色や経験が、たくさんあります。発達障害の有無に関わらず、子育てはネガティブもポジティブも両方を味わうもの。
だから「発達障害育児だから大変」と心がいっぱいになるのも自然なこと。むしろその不安や怒り、悲しさをきちんと感じ切った先に、必ず道が開けます。
悲しいことも楽しいことも抱きしめながら、親子で少しずつ素敵な日々が重ねていけますように。その子だから見える世界を一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。
.png)
森久保 智香
発達障害育児に悩むママを笑顔にする専門家/東京都在住。中2の長男・小4の次男の母。
次男の発達特性の経験を起点に、Instagramで“親子の生きづらさを軽くする伴走支援”を発信中。
「やり方(発達の知識)×マインド(親の思考の整え)」の両輪を大切にし、発達の凸凹に家庭でアプローチ。
Instagram:@shoryu.onlyone
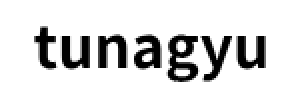

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 258
閲覧数: 258
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 244
閲覧数: 244
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 203
閲覧数: 203