── RINAさんインタビュー
あなたは、わが子の発達障害の特性に戸惑い、つい周りの視線を気にしていませんか?
確かに、子どもが予想外の行動を取ると、親は冷や汗をかき、学校や地域との関係にも不安を抱えがちですよね。
結果、どう接すればいいのか分からず “孤立” や “自己否定” に悩む保護者の方も少なくありません。
でも実は、子どもの困り感への対処を「特別扱い」ではなく「配慮」として捉え、環境をほんの少し整えるだけで、親子双方のストレスは驚くほど軽減できるんです。
そこで今回は、最重度知的障害・自閉スペクトラム症の次男を育てながら、親の会代表として活動するRINAさんに、理解と配慮のポイントを伺いました。
――今まさに悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
■地域に根差して広がる確かな変化
最重度知的障害・自閉スペクトラム症の次男の子育てをきっかけに、RINAさんは高知で発信とコミュニティづくりを続けています。
Instagramでの等身大の言葉に加え、2016年設立の親の会では年2回の講演会を開催。
また、まだ支援につながれていない家庭の声を丁寧に聴き、具体的な対処を一緒に考える場を開きます。
家庭の中でできる小さな配慮から、地域の支援資源への橋渡しまで——必要なサポートへ“たどり着ける道筋”を増やしていきます。

■「特別扱い」ではなく「配慮」という視点
RINAさんに「特別扱い」と「配慮」について伺いました。
「配慮は、その人にとって必要なことを当たり前に行うだけのこと。
みんなが同じ状態で生活できるよう整える行為であって、特別扱いとは本質的に別物です」
例えば「メガネ」。
視力が弱ければメガネやコンタクトを使う。
それと同じく「字を書くのが難しい子には写真ノートを貼る」「机の軋む音が苦手な子には脚にテニスボールをかぶせる」――必要な支援をすることが配慮だと語ってくれました。
■困り感に気づくための“なりきり”観察
問題行動と呼ばれる行為の裏には、必ず子ども自身の苦しさがある。
「“支援する=その人になる”っていうことで、自分がその立場だったらどうだろうと考えます」
RINAさんは「その子になる」という考え方を勧めてくれました。
たとえば手先が不器用な子の感覚を知るために、手袋を何枚も重ねて細かい作業することを想像してみる。
“できない”のではなく“ものすごく大変”だと実感できると、支援の視点がガラッと変わります。
■環境を変えれば子どもは動き出す――次男のエピソード
最重度知的障害のある次男(14 歳)は体格が大人並みだけどIQだけでみると、1歳半から2歳ぐらい。
それでも小5の頃から 45 分着席できるようになったといいます。
「先生が“座りたくなる環境”を整えてくれました。
本人が“ここにいたい”と思えれば、行動はぐっと変わっていきました」
■具体的な配慮アイデア集
音刺激の軽減:机や椅子にテニスボールを装着/ノイズキャンセリングヘッドフォンの許可
見通しの可視化:時程表に「次の教科+持ち物+場所」を記載
視界の整理:パーティションや布で不要な情報を隠し、集中できる空間を確保
選択肢の提示:「したいこと/したくないこと」を本人に確認し、自立を妨げない範囲で手を引く
「“何をしてほしいか”“何はしてほしくないか”を聞くだけで、余計な支援でその子の自立の力を奪わずに済みます」

■観察こそ支援の第一歩——子どもを見る前に、まず自分を整える
子どもの「声が出るタイミング」や「イライラが始まる場面」は、じっくり観察すれば少しずつ見えてきます。
ところが、大人に心の余裕がないと、そのサインを見逃しがち。
「 だからこそ 「まずは親自身を観察すること」 が欠かせません」
とRINAさんは5年間、繰り返し伝えてきました。
自分の疲れや感情を把握してこそ、子どもに起きていることを冷静に捉え、適切な支援へつなげる視点が育つんです。
■親の心の余裕が、子どもを支える力になる
子どもの困り感に気づくには、まず大人自身に心の余裕が必要です。
「自分が整っていないと、子どもの小さなサインを見逃してしまう」
イライラや疲れを抱えたままでは、子どもの行動を冷静に観察できず、「なぜ困っているのか」に目を向けることが難しくなります。
だからこそ、まずは親自身が自分の感情や疲れに気づき、“今の自分を受け入れること”。
その余裕が生まれることで、子どもの行動の背景を丁寧に見て、適切な配慮へとつなげられるようになるのです。
■行き詰まったら、視点を増やす
努力しても状況が好転しないときには、信頼できる人や場に相談してみることが大切です。
ひとつの視点に頼るのではなく、いろんな立場の人から意見をもらうことで、自分だけでは気づけなかった見方や対応策が見えてきます。
実際にRINAさん自身も、困ったときには「学校・療育・親の会など、少なくとも3人くらいに相談してみる」ことを心がけてきたそうです。
「視点が増えれば“別の道”が見つかる。
1人で抱え込まず、自分だけでどうにもならないことをまず知ってほしいです」

■現実と向き合うまでの揺らぎと、親のセルフケア
次男の特性に気付いたのは生後9か月。診断確定までの1年間は「この子、しゃべらないから知的な障害があるかも。
でも明日喋るかもしれない」「やはり自閉症かも」と感情のジェットコースターが続いたという。
「受け入れられたのは3歳ごろ。
“私が現実を受け止めなければ、この子は前に進めない”と腹をくくった瞬間でした」
でも、泣いたり怒ったり揺れたりする自分を責めなくていい。
感情を押し殺さず“私は今つらい”と認めることが大切だと話してくれました。
■さいごに
まさか我が子に発達障害——となると、生まれる前も直後も気づけず、覚悟が決めにくくて受け入れられないものです。
けれど 「現実は変わらない」 障害をまず受け止めることが必要です。
そのうえで しんどいときは「しんどい」、怒りたいときは「怒り」を声に出し、イライラなどの感情に蓋をしないで「そんな自分も許してあげる」。
感情を一つ一つ認める作業こそが、心の疲れを癒やす第一歩になります。
自分を責めず、助けを求めることを恐れない。そんな大人の姿勢が、子どもたちの未来を明るく照らしていくのです。
.png)
RINA
発達障害児の親の会代表として活動しながら、Instagramで最重度知的障害+自閉症の次男(支援学校中学部2年生)との日々や、母としての心の整え方を発信。
「ママ自身が幸せであることが最優先」という思いを軸に、きょうだい児育児や自分らしい生き方を等身大で伝え、「期待はせずに、希望を持つ」という経験を多くの保護者に届けている。
Instagram: @rina10deguchi30
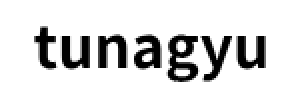

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 245
閲覧数: 245
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227