── うえみん先生 インタビュー
あなたは、ついつい子どもが友達とトラブルを起こしたとき、「うちの子が可哀想」「相手の子が悪い」と決めつけていませんか?確かに、わが子が傷ついている姿を見るのは、親として何よりも辛いものです。
結果、親が過度に介入してしまい、逆に関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
でも実は、子ども自身の力を信じ、適切な距離感で関わるだけで、トラブルは“学びの機会”に変えることができるんです。
今回は、元・小学校教員で現在は「クセ強継続相談」を通じて親子をサポートしているうえみん先生に、友達トラブルへの具体的な向き合い方を伺いました。
■ 教員15年の経験から立ち上げた「クセ強継続相談」
「私は15年間、小学校の先生をしてきました。通常級、支援級を通して、1年生から6年生まで担任を経験してきたんです」
その経験をもとに、現在は“クセの強い子とお母さんのための個別継続相談”――通称「クセ強継続相談」をオンラインで行っています。
子どもの宿題や癇癪、発達の不安から、先生との関係、そして友達トラブルまで。
さまざまな悩みを抱える親子に寄り添いながら、「子育てをアップデートする」支援を続けています。
 (16).png)
■「子どもを育てるのは学校ではなく“家庭”」という信念
「先生として働いていたとき、子どもをサポートするには“お母さんとの連携”が何より大切だと感じていました。
でも、学校という立場では、保護者に踏み込むにはどうしても限界があったんです」
子どもを育てるのは学校ではない。自信をもって子育てできるお母さんを増やしたい”その思いを胸に、先生という肩書きを手放し、家庭の応援者として歩み始めたのが、うえみん先生の原点です。
■ 「友達トラブル」に多いケースと、親の誤解
よくあるのは、「叩かれた」「暴言を言われた」「仲間外れにされた」といった直接的なトラブル。
でも実際には、【言いたいことが言えない】【流されてしまう】【相手にどう思われるか気にしすぎてしまう】といった悩みもとても多いです。
こうした相談に共通しているのが、「うちの子が被害者だ」と信じている親の視点。
「もちろん、親なら誰でもそう思います。でも、子ども同士の関係はもっと複雑で、“加害と被害”では語れないことも多いんです」
■ 学校は“他者との関係性を学ぶ場”
「家庭の中では学べない“他人との関わり方”を学ぶのが、学校です」
だからこそ、トラブルを“避けるべきもの”として見るのではなく、「この経験から何を学ばせてあげようか?」
「どんな力を身につけるチャンスになるだろうか?」という視点で捉えることが大切だと、うえみん先生は語ります。
■ 介入しすぎは逆効果。「線引き」の考え方
「関わることは悪くないんです。ただ、“やりすぎ”がこじれの原因になることが多い」
たとえば、子どもは「もう気にしてない」と言っているのに、親が納得できずに親同士のトラブルに発展するケース。そうなると、親同士の価値観のズレで関係が悪化することも。
うえみん先生は、関わり方の判断軸として次の3点を挙げています。
子ども本人がどう捉えているか
単発で起きている事なのか継続で起きている事なのか
子どもの努力や工夫で対応できそうか
「親の出番は“なるべく後回し”が基本です」
■ “見守る”という関わり方とは?
「“見守る”って、ただ放っておくことではありません」
うえみん先生によれば、それは
・子どもの話をよく聞く
・考える力を引き出す
・決めたことを応援する
という3つのステップ。
この「信じて応援する」というのが難しいですね。「信じる」ためには「この子は大丈夫」という証拠を集めなければいけません。親が、わが子のできているところに注目する視点を持つ必要があります。
「応援する」ためには、子どもが応援されていると思える関わりをすることが大事です。頑張れ大丈夫と表面だけの応援ではなく、子どもの思いに共感しながら話を聞くこと。
そして、あなたにできることは何かと一緒に考えていくことが大事です。
 (18).png)
■ 話してくれない子どもに、どう向き合うか
「話さない子には、まず信頼関係の見直しを」
親子の関係が崩れていると、子どもは「どうせ否定される」と感じてしまい、話したがらなくなります。ですので、まず子どもとの信頼関係は良好なのかを確認しましょう。
親子の信頼関係が良好でそれでも話さないなら、それは“親の出番ではない”というサインかもしれません。子どもが“自分で考えたい”という気持ちを持っているなら、尊重してあげることも大切な選択です。
■ 学校や相手の保護者との連携のコツ
「まず、“一言目に要求を出さないこと”です」
大切なのは、
・自分の感情を伝える
「こういうことで困ってます」「こういう事で悩んでいるんです」
・家での対策を共有する
「家でこういうことをやったんですよね」「子供にこういう話をしたんですよね」
・一緒に考えてもらえるか、相談する
「こういうことができるかどうか一緒に考えていただけませんか」
この3つを意識すれば、クレームではなく“対話”になります。
「伝え方一つで、印象も関係も変わりますよ」
 (19).png)
■ 今、悩んでいる親御さんへ
「悩んでいる子を見るのは、親として本当に辛いですよね。早く平穏な日常を取り戻したい、そう思うのは当然です」
でも、今あなたの子どもが経験しているトラブルは、“成長の入り口”でもあります。
「先回りして解決しても、また形を変えて繰り返します。大事なのは、子どもが自分で考えて、決めて、行動して、責任を取ること」
子どもの背中を信じて、ゆっくりと見守っていきましょう。
■さいごに
子どもの友達トラブルは、親としてとても心配な出来事です。でも「今、何を学んでいるのか?」という視点を持つことで、トラブルは成長のきっかけになります。
大切なのは、親が“正す”のではなく、子どもが“考える”ことを支える姿勢。関わり方に迷ったら、まずは「見守る」を意識してみてはいかがでしょうか?

うえみん先生
元・小学校教員(15年)。通常級・支援級・通級すべての学年を担任した経験をもとに、現在は「クセの強い子とお母さんの個別継続相談(クセ強継続相談)」をオンラインで提供。
宿題・癇癪・発達の悩み・人間関係など、小学校時代に起きる“親子の困りごと”に寄り添い、子育ての見直しをサポートしている。
うえみん先生の詳しい情報はこちらから
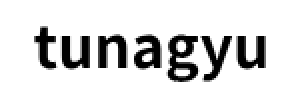
 (20).png)
 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 258
閲覧数: 258
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 245
閲覧数: 245
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 203
閲覧数: 203