——子どもの自信を育む専門家 ゆりさんインタビュー
子どもが何かに挑戦しているとき、つい「こうしたほうが早いのに」と手を出してしまった経験はありませんか。
失敗させたくない、散らかされたくない、早く終わらせたい。
でも、その一歩をぐっとこらえて見守ることで、子どもは自信を積み重ねていくんです。
今回は、Instagramで「子どもの自信を育む専門家」として発信し、モンテッソーリ教育やコーチングを取り入れた子育てサポートを行う ゆりさん にお話を伺いました。
■学童の先生から、親子を支える専門家へ
ゆりさんは、Instagramで『子どもを信じて待てるママになる』をテーマに発信しています。
オンラインでモンテッソーリ教育やコーチングを活かした子育てサポートをしていて、4月からは週に1回東京都の町田で『見守り付き子育てひろば~こどレスひろば~』も運営しています。
「子どもがシェフになって料理し、家族にふるまう『こどもレストラン』を企画し、食と音楽の世界旅行という副題にちなんで、世界の音楽を私が演奏するなど、演奏家としても親子向けに活動しています」
もともとは学童保育で10年間、主に小学生の放課後を支えた経験の持ち主。保育士資格も持ち、リトミックなど保育園でのお手伝いもしてきました。
その豊富な現場経験が、今の活動の土台になっています。

■つい手を出してしまう2つの理由
多くの親御さんが口にするのは「つい手を出してしまう」という悩み。
「親がつい手を出すのは“失敗させたくない”気持ちと、“大人の事情で待てない”気持ちから」
ですが、失敗は学びのチャンス。
「失敗=悪いこと」という無意識の思い込みを外していくと、子どもの自立と安心は両立できるんです。
ゆりさんによれば、失敗を「避けるべきこと」ではなく「成長の糧」として受け止められるかどうかが大きな分かれ道。
失敗した後の子どもの行動を一緒に考えることこそが、未来の力につながるのだそうです。
■「見守る」とは、ただ放っておくことではない
「子どもをよく観察し、“できる存在”と信じることが大切です」
ゆりさんが強調するのは、見守りとは放置ではなく“信じて観察する姿勢”だということ。
モンテッソーリ教育では「自己教育力」と呼ばれるように、子どもには自ら成長していく力があります。
大人の役割は「できない」と決めつけて口を出すことではなく、環境を整えながらその力を信じて支えること。
そうすることで子どもは「やってみたい」という気持ちをのびのび発揮できるのです。
■手を出さずに待つ、その判断基準
では「今は手を出さず待とう」と判断する基準はあるのでしょうか。
「危険がないかを確認し、“子どものためか、自分の不安のためか”を問いかけてみてください」
危険でない限りは、5秒でも10秒でもいいので待ってみる。
その間に子どもが「もう1度やってみよう!」と自分で挑戦を続けるかもしれません。
そして「手伝って」と助けを求めてきたときにだけ、必要なサポートをするのが基本姿勢です。
大切なのは、親が「今手を出そうとしているのは、子どものため? それとも自分の焦りや不安から?」と立ち止まって振り返ること。
そうした一瞬の内省が、見守る力を育てるのだといいます。
■見守るときの声かけと“沈黙”の工夫
「『やってみる?』と問いかけ、過程を認めることが大切です」
ゆりさんが大事にしているのは、子どもに選択の余地を残す声かけ。
「やってみよう」では強制に近くなりますが、「やってみる?」なら子どもの気持ちを尊重できます。
さらに「挑戦しようと思ったんだね」「昨日よりここまでできたね」と、結果よりも過程を認める言葉が自信につながります。
一方で、あえて言葉をかけない工夫も欠かせません。
表情や目線で「見ているよ」と伝えるだけで子どもは安心します。
必要なときにだけ「手伝えることある?」と聞き、サポートは最小限にとどめます。
「全部やってしまうと“自分にはできない”という思い込みが育ってしまいます。
最後は子ども自身に“できた”という体験を残すことが大切です」

■自信を削ぐNG行動とは
本来できるはずのことを親が全部やってしまうと、子どもは「自分にはできない」と思い込んでしまいます。
さらに「ほら言ったでしょ」と結果だけを否定したり、「上手だね、すごいね」と結果ばかりを褒めるのも要注意。
「できることを奪ったり、結果だけで評価するのはNGです」
一見ポジティブに見える言葉でも、結果ありきの評価は挑戦する気持ちを削いでしまいます。
大切なのは「やってみようとしたね」「昨日より進んだね」と、挑戦の過程や努力をしっかり認めること。
そこにこそ、子どもの自信を支える力があるのだといいます。
■見守りが育む3つの力
1. 主体性——「自分でやろう」と思える力見守る関わりの中で最初に育まれるのは「主体性」です。
子ども自身が「やってみたい」と思い、その気持ちを行動に移せるようになります。
大人が先回りせず信じて待つことで、その芽は自然に育ちます。
次に育つのは粘り強さ。失敗しても「もう一度」と挑戦できる気持ちです。
失敗を否定せず見守ってもらえることで、「できるようになるまで続けてみよう」という心が強くなっていきます。
最後に大きく育つのが自己肯定感。
昨日できなかったことが今日できたとき、子どもは「自分はできる」という実感を積み重ねます。
その経験が揺るぎない自信につながっていきます。
■日常の中で芽生える力
ゆりさん自身も娘さんとの生活の中で、この3つの力が育っていく様子を実感しているといいます。
ボタンの練習
パジャマのボタンを「自分でつけたい!」という娘さん。
でもまだまだつまむ力が弱くてなかなかできませんでした。
ゆりさんがボタンを半分穴に通してから娘さんにやらせたり、指先を鍛える遊びを取り入れたりしながら、本人のやりたい気持ちを尊重してきたそうです。
はじめて、最初から最後まで自分で出来た時の「できた!」という声と表情は、今でも忘れられないそうです。
最初はピースをどこに置けばいいかも分からなかったパズル。
それが今では60ピースにも挑戦できるように。
小さな「できた」の積み重ねが「〇〇(自分の名前)ちゃんはできる!」という口ぐせになり、新しい挑戦へと広がっていきました。

■親も一緒に積み重ねる“小さな成功体験”
「見守るとは子どもを信じること。
そしてそれは親自身を信じることでもあります」
ゆりさんは、見守ることを“親子の共同成長”と表現します。
たとえば昨日より少しだけ待てたなら、それも親にとっての小さな成功体験。
子どもの挑戦を尊重できた自分を認めることが、自信につながっていきます。
さらに「許せる範囲を自分で決めていい」とも語ります。全部を完璧に受け入れる必要はなく、「ここまでは待つ」とルールを決めれば無理なく続けられる。
見守りは、子どもを育てるだけでなく、親自身の成長もそっと後押ししてくれるのです。
■今日から始める一歩——矢印を自分へ
「“早く!”と言ってしまう場面を振り返ることから始めてみてください」
ゆりさんが提案するのは、とてもシンプルな第一歩。
朝の慌ただしい時間や、疲れている夜に手を出してしまう背景には、親自身の不安や疲労が隠れていることがあります。
なぜその行動が出たのかを知ることで、自分を理解し、少しずつ行動を変えていけるのです。
見守る力を育てるには、子どもにだけ矢印を向けるのではなく、自分自身にも矢印を向けることが大切。
子どもを信じるという行為は、やがて自分を信じる力にもつながっていきます。
■さいごに
子どもの成長は、親が一歩下がって“見守る”ときに大きく花開きます。
失敗も成功もすべてが学び。昨日より少しだけ待ってみる——その小さな一歩が、子どもの自信と、そして親自身の成長を同時に育んでいきます。
「待つのは難しい」と感じる日があっても大丈夫。
大切なのは完璧であることではなく、少しずつ積み重ねていくことです。
子どもの「できた!」という笑顔と、親の「待てた!」という安心。その小さな喜びの連続が、やがて大きな力になります。
明日、ほんの数秒でもいい。
いつもなら手を出してしまう場面で、少しだけ待ってみませんか?
その一瞬が、親子にとってかけがえのない成長のきっかけになるかもしれません。
.png)
ゆり|子どもの自信を育む専門家
モンテッソーリ教育とコーチングを取り入れた子育てメソッドをもとに、オンラインで子育てサポートを実施。
「見守り付き子育てひろば~こどレスひろば~」「こどもレストラン~食と音楽の世界旅行~」など、親子がつながる場を企画。
学童保育で10年にわたり1000人以上の小学生と向き合った経験を持つ。
輝きベビーシニアインストラクターとして、“子どもを信じて待てるママ”を増やす活動を続けている。
ゆりさん Instagram:@yuri__kosodate
こどもレストラン Instagram:@kodomo.rest
こどレスひろば(見守り付き親子の居場所)Instagram:@kodoreshiroba_machida
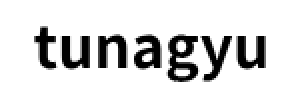

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 272
閲覧数: 272
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 (12).png) 閲覧数: 256
閲覧数: 256
 閲覧数: 254
閲覧数: 254
 閲覧数: 245
閲覧数: 245
 閲覧数: 229
閲覧数: 229
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 227
閲覧数: 227
 閲覧数: 203
閲覧数: 203